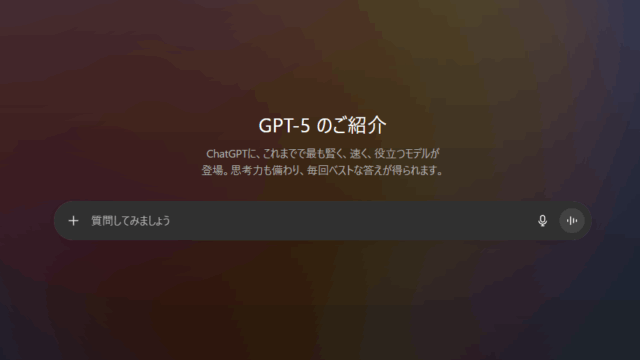宣伝失礼しました。本編に移ります。
ユナイテッドアローズ、TSIホールディングス、アダストリア、バロックジャパンリミテッドが共同で立ち上げた「アパレル物流研究会」が、国内外で相次いで概念実証(PoC)を進めています。象徴的なのが、2025年6月にスタートしたECモール向け共同配送。競合4社が荷物を“まとめて運ぶ”という業界横断の実装は、配送効率とサービスの安定性を同時に高める打ち手として注目を集めています。さらに7月下旬からは海外調達の上流段階での共同輸送にも踏み込み、アパレルの「運ぶ」をゼロベースで再設計しようとしています。
ニュースの核心──発足の事実と狙い
アパレル物流研究会は2023年10月に発足。目的は明快です。第一に、各社の個別課題を持ち寄り、業界共通のボトルネックを可視化すること。第二に、将来的な物流インフラの一部共通化を見据え、共同で議論・実験・検証・仕組み化に取り組むこと。第三に、参画企業を拡大し、得られたメリットを業界全体へ波及させること。ファッションは商流が複雑で、輸配送を外部に依存しやすい構造ゆえ、単独企業では対処しきれない課題が多い──この直視から始まった取り組みです。
背景には「2024年問題」「2025年問題」があります。ドライバーの時間外労働規制強化や高齢化に伴う人手不足は、輸送コストや納期の安定性を直撃します。長距離エリアでは荷量の薄さから日次納品が維持できないケースも顕在化し、従来のやり方の延長線上に持続可能性を見出すのが難しくなりました。だからこそ、競合同士が利害を乗り越えて“後工程を共通化する”方向に舵を切ったのです。
ECモール向け共同配送──“一本化”がもたらす安定と拡張性
共同配送のPoCは2025年6月に開始され、現在も継続中です。従来は各社が個別契約のトラックでECモールの倉庫へ納品していましたが、PoCでは近接する拠点の貨物を一度集約し、運送会社で積み替えてから、各モールの拠点へ一括納品するスキームに刷新しました。具体的には、ユナイテッドアローズの茨城拠点、バロックジャパンの埼玉拠点の貨物を、アダストリアの茨城・群馬の拠点に集め、同社貨物も合わせて束ねたうえでモール倉庫へ送る構図です。結果として、ルートの安定性が増し、メニュー拡張の余地が広がるという評価が得られました。
ポイントは「荷量の確保」です。共同輸配送の難所は積載率と時間調整にありますが、出荷元や配送先を粒度高く束ね、十分なボリュームを形成できれば、積載効率は自ずと改善します。拠点の地域や商材の性質、納品形態が似通うプレイヤーをうまく“編成”すれば、新ルートを開拓しやすく、曜日・時間帯別の運用メニューも設計しやすくなる。参画企業が増えるほどネットワーク効果が働き、幹線の頻度や安定性はさらに高まります。
共同配送の効能は事業者側の効率化に留まりません。商業施設やモールの受け入れオペレーションも、ブランド横断の納品一元化で平準化されやすく、バックヤードの混雑や待機時間の抑制に寄与します。施設側の省人・省スペースの設計が容易になり、結果として納品先も含めたサプライチェーン全体の生産性がじわりと底上げされていきます。
海外共同輸送──生産地に遡り“上流で束ねる”
研究会は海外調達でもPoCを始動しました。7月下旬からベトナム発の試験共同輸送を展開し、フォワーダー1社に情報を集約して上流での輸送コントロールに挑んでいます。工場・製品の詳細を共有しないガバナンスを維持しつつ、スケジュールが合致した貨物から順次まとめて出す。中距離航路への展開や、輸配送以外の共同化(通関・デバンニング・資材調達など)への拡張も見据えています。
「海外で運べないリスク」は港湾ストやスペース逼迫、為替・地政学影響など複合要因で表面化します。上流で束ねる共同輸送は、便の取り逃しやスポット運賃の急騰に対する“緩衝材”として働き、計画のブレを吸収する余地を生みます。国内の共配と海外の共同輸送を一気通貫で設計できれば、納期の安定化と在庫回転の改善はさらに現実味を帯びます。
なぜいま共通化なのか──“運べない時代”の前に動く
ドライバー不足、長時間労働抑制、賃上げ圧力、運賃の構造的上昇──個社最適の積み上げでは限界があります。共同化は「走行台数を減らし、積載率を上げる」という単純明快な原理に立ち戻り、ネットワーク全体の総量効率を高めるためのアプローチです。過去にはTSIとワールドが同一施設向けの共同配送を展開し、トラック削減と環境負荷低減、ドライバー不足緩和の方向性を実証しました。今回の“四社連合”は、その発想をより広域・高頻度のオペレーションへと拡張しようとしています。
アパレル企業は全国約2500社とも言われ、SKUも季節も多様です。この“多様性の塊”を束ねるには、カレンダー、ロケーション、SKU特性の三点で共通性を抽出し、オペレーションを再設計する必要があります。共同化の価値は、単に運賃を下げることではなく、「安定性と拡張性の両立」をネットワークとして担保するところにあります。
各社の“武器”──共配を下支えする基盤投資
ユナイテッドアローズは、センコー流山ロジスティクスセンターをマザー倉庫に据え、t-Sortによる仕分け自動化を採用。2025年にはロボティクス自動倉庫「AirRob」の運用を開始し、1日3.5万~4万ピースの入出荷をこなしつつ保管キャパシティの段階的拡張を進めています。既存オペレーションを止めずに導入する手法で、OMO時代の在庫一元管理を高密度・高生産で回す設計に踏み出しました。
TSIホールディングスは、アリババクラウドのWMS(ツァイニャオのスマートロジスティクス技術を活用)を導入し、国内外で在庫・輸送の可視化とAIによる作業平準化、需給予測を強化。さらに2018年からロボット倉庫の取り組みをグループ物流子会社TSIプロダクションネットワークをハブに進め、BPRと現場の省人・安定化を同時に推進してきました。クラウド×ロボティクスの両輪で、波動対応と拠点横断の運用統制を深化させています。
アダストリアは、toB物流の再編を見据えて茨城県常総市にグループ最大級の常総DCを開設。EC側は茨城西物流センターを全面リニューアルし、AGVや移動棚を大規模に導入することで、出荷能力の大幅増と“人が主役”の安全・快適な職場づくりを両立しました。マルチブランド・マルチカテゴリーの現場要件を踏まえた設備計画により、共同配送の“受け皿”機能も強化されています。
バロックジャパンはRFID活用の先行例として知られ、物流センターと店舗の両方で在庫精度と作業速度を飛躍的に高めています。たとえば店舗棚卸は、数千点規模でも少人数・短時間で完了できる水準まで短縮。センター側ではソーター連携でのスループット向上が確認されており、データドリブンなMD・防犯・顧客体験の改善にも波及しています。標品識別の高度化は、共配網での合流・分流や誤混載防止にも効いてきます。
共同化の本質的価値──“積む・届ける”の精度が利益を生む
共配のKPIは輸送コストだけではありません。乗務員の拘束時間、待機時間、到着時刻の分散、施設側の受け入れ処理時間、投入・引当の在庫回転、CO2排出原単位──これらを束ねて“一本”として最適化するのが共同化の肝です。個社の積載率を3~5ポイント引き上げるより、ネットワーク全体で10ポイント上げるほうが達成確率も持続可能性も高い。その設計に必要なのは、「どこで合流し、どこで分流するか」というアーキテクチャ思考です。
ECモールの視点でも、共通スロットや納品要件の標準化が進めば、受け入れ側のピークカットが可能になり、倉庫内の波動と要員配置を平準化できます。モール各社の物理・デジタルのインターフェースを磨くことで、納品から検収・可売化までのリードタイム短縮が現実味を帯び、売り逃し削減と在庫圧縮に寄与します。共配は、売上ではなく利益を増やす“静かな成長装置”です。
商業施設・物流企業への波及──三方良しの設計へ
商業施設では、同一施設に複数ブランドを持つ4社の納品が一元化されれば、荷受けカウンターの混雑が緩和され、警備・搬入動線・エレベーター運用の最適化が進みます。物流企業は、共配ルートの定期運行化で車両・乗務員の稼働計画が立てやすくなり、稼働率の向上が原価の安定化に直結します。共同化は荷主だけでなく、納品先と運ぶ側の双方に確かなベネフィットをもたらします。
不確実性が高まる中、荷主と物流企業の“共創”は競争力の源泉になります。共同化の枠組みは、価格交渉の土俵ではなく、成果配分の土俵へ。KPIの可視化と共通ルールの下で、節減効果とサービスレベル向上を分かち合う仕組みが、次の産業標準になるはずです。
課題と打ち手──データ、契約、現場の三位一体で
第一の課題はデータガバナンスです。WMS/TMSの仕様が異なる企業間で、必要最小限の情報のみを安全に交換し、運用上の最適化に必要な粒度を確保する設計が求められます。品番・箱数・容積・重量・納品時間帯・バース制約など、共配に必須のデータ項目を共通フォーマット化し、差分はアダプタで吸収する。生産地・輸送区間・納品区間で開示レベルを段階化する“レイヤード・シェアリング”が現実的です。
第二は契約設計です。節減効果とリスクをどう分かち合うか、荷主間・荷主と運送会社間のレベニューシェアとSLAを具体化する必要があります。欠便・遅延・波動時の優先順位や、増便・臨時便の手当、運賃改定のトリガー、CO2削減効果の計測と配賦──これらを曖昧にしたままでは、現場は動きません。定量KPIと逸脱時の自動的な調整ルールを契約に織り込むのが肝要です。
第三は現場設計です。集約拠点における積み替え動線、ヤード回転、バース割当、ダンボール規格・パレタイズ・ラベリングの標準化といった“手触りのある改善”が、共配の成否を左右します。RFID・スキャン・計量の一致精度を高め、誤混載・誤納品の確率を極小化する。人とロボットを混在させるオペレーションでも、疲労とヒューマンエラーを抑えるUI/UXの設計が欠かせません。
ロードマップ──12カ月で到達すべき具体ステップ
まずはECモール共配の“メニュー化”です。曜日別・時間帯別・拠点別の標準スロットを設け、参加企業にとって選びやすいカタログにする。次に、共通データ辞書と連携APIの最小実装版(MVP)を定義し、3カ月刻みでバージョンアップする。海外はベトナムの安定運用を最優先に、短距離/中距離の二軸で便の確保と時刻表化を進める。いずれもKPIは「積載率・オンタイム率・CO2原単位・可売化時間」を中核に据えるべきです。
さらに、参画企業を段階的に広げ、地域クラスターごとに“最適な合流点”を増やすことが重要です。アパレル以外の隣接カテゴリー(雑貨・コスメ・小型家電など)とのマルチテナント共配も、容積と重量の相性次第で現実味を帯びます。研究会がハブとなり、共配の“設計図”を公開しながら実装コミュニティを広げることが、日本の小売物流の持続可能性を高い次元で下支えします。
結論──“静かな革命”はもう始まっている
四社が描いたのは、値下げありきの物流ではなく、「安定性×拡張性×持続可能性」を同時に満たすネットワークの再設計です。ECモール向け共同配送はその象徴であり、海外調達の上流で束ねる共同輸送は“第二幕”です。技術投資と現場知の掛け算、データと契約の設計、そして仲間づくり。小さく始めて大きく育てるこのアプローチは、アパレルに限らず日本のリテール物流全体に波及しうる「静かな革命」です。次に動くのは、誰かではなく“あなたのサプライチェーン”です。いまなら、間に合います。
当社では、AI超特化型・自立進化広告運用マシン「NovaSphere」を提供しています。もしこの記事を読んで
・理屈はわかったけど自社でやるとなると不安
・自社のアカウントや商品でオーダーメイドでやっておいてほしい
・記事に書いてない問題点が発生している
・記事を読んでもよくわからなかった
など思った方は、ぜひ下記のページをご覧ください。手っ取り早く解消しましょう
▼AI超特化型・自立進化広告運用マシンNovaSphere▼

![デジマラボ [Digima Labo] by NpvaSphere(旧チャンキョメ)](https://digima-labo.com/wp-content/uploads/2023/06/logo_dezimalabo_2212763.png)