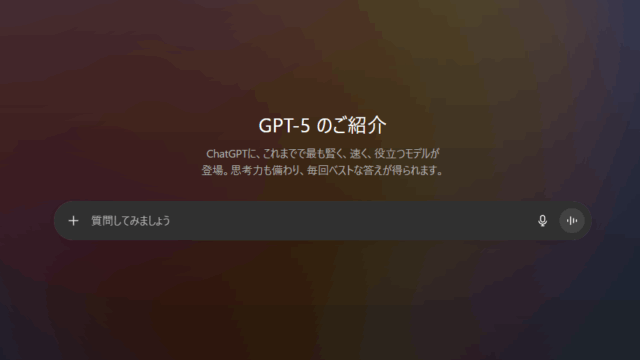ぶっちゃけ「知識」が必要なのではなく、今すぐ結果が欲しい!という方へ
宣伝失礼しました。本編に移ります。
2025年秋、国内のメディア環境を俯瞰すると、Z世代のテレビ接触は単なる減少ではなく再編の局面にあります。最新の大規模調査では、10〜20代の半数以上が毎日30分以上テレビコンテンツを視聴しており、同時にYouTubeや見逃し配信、SNSと立体的に行き来する「複層視聴」が定着しています。結論から申し上げます。Z世代は“テレビを捨てた”のではありません。“テレビの使い方”をアップデートしたのです。本稿では、直近の一次情報と市場動向を束ね、時間帯・ジャンル・配信・広告・編成の各視点から、Z世代の真の視聴実態を読み解きます。

「半数が毎日30分以上」──数字が覆す“テレビ離れ”
2025年6月実施・有効回答1万人の最新調査では、10〜20代の過半数が毎日30分以上テレビコンテンツを視聴していることが示されました。高年代ほど視聴時間が長いという構図自体は有効である一方、若年層の「ゼロ視聴」仮説はもはや当てはまりません。さらに、視聴の定義は放送電波だけではなく、番組IPの配信や見逃し視聴を含む“テレビコンテンツ全体”へシフトしています。言い換えると、テレビは「スクリーンとしてのテレビ」と「番組としてのテレビ」に分解され、Z世代は後者に粘着度高く接触しています。家庭でテレビが点いた瞬間に主体的に座るのではなく、スマホで話題を見つけ、必要なときだけ番組を掴みにいく──これが日常です。【図解:毎日30分以上のテレビ視聴割合(概念図)】
年代別に見る“過半数ライン”の位置
10代|■■■■■■■■■■■■■──────────
20代|■■■■■■■■■■■■■■─────────
50代|■■■■■■■■■■■■■■■■■■■────
60代|■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■──
凡例:■は視聴者のボリューム感(概念)。若年でも過半数が30分以上。ピークは20時テレビ・21時ネット──“1日の山”でわかる共存関係
Z世代の接触リズムを時系列で見ると、20時台にテレビの視聴行動が高まり、21時台にはネット動画、22時台にはSNSがピークに達するという“階段型”の山が確認できます。朝の7時台には天気・情報番組の視聴がやや伸びる一方、日中はネット動画優位。つまり、テレビとネットは同一時間帯で奪い合うのではなく、1日の中で役割を分け合っています。【図解:Z世代の接触リズム(概念)】
時刻→ 7時 12時 18時 20時 21時 22時
テレビ ──▂▂──────────▇▇▇──────
動画 ──────▃▃▃───────▇▇▇▇────
SNS ────────────▅▅──────▇▇▇▇
解説:夜は「テレビ→動画→SNS」の順で山が連続する“階段型ピーク”。上位はアニメと国内ドラマ、バラエティ・お笑い・スポーツが拮抗
Z世代の番組嗜好は、アニメと国内ドラマが強く、次点で娯楽バラエティやお笑いが並びます。スポーツは“イベント時爆発型”で、普段はライト、ビッグマッチはヘビーという二層の需要が共存。ここで重要なのは、ジャンルそれ自体よりも「発見経路」です。多くの若年視聴は、SNSのクリップや切り抜き、出演者の短尺動画がトリガーになり、TVerや公式チャンネルの見逃し視聴へ遷移します。つまり、視聴の起点は番組表ではなくフィード。番組がSNSの言語で“引用可能”に設計されているか否かが、Z世代の接触を大きく左右します。【図解:好きなテレビ番組ジャンル(Z世代上位)概念】
アニメ ━━━━━━━━━━━━━
国内ドラマ ━━━━━━━━━━
バラエティ ━━━━━━━━
お笑い ━━━━━━━
スポーツ ━━━━━━
注:上位ほど長尺・シリーズ消費が起きやすく、SNSでの話題化も強い。TVerが橋渡しする“放送⇄配信”の往復運動
民放公式の見逃し配信はZ世代の視聴導線の中心に位置しています。リアルタイムで見逃した番組をTVerで補完し、その視聴体験が再びSNSへ還流して話題を増幅。さらに次回放送のリアルタイム視聴へ回帰するという“循環”が、若年層で一般化しています。冬ドラマ期やスポーツライブ配信など、きっかけが明確なタイミングでは、TVerの月間利用規模や再生数が跳ね上がり、放送と配信の相互補完が定常化しています。【図解:Z世代の視聴循環(概念)】
SNS話題 → TVer見逃し視聴 → クリップ共有 → 次回リアルタイム
↖────────────増幅────────────↙
解説:見逃しで“追いつく力”があるため、話題化が連鎖して輪が拡大。リビングで“ネットを見る”時代──コネクテッドTVが若年の選好を変える
スマホ中心の世代であっても、コネクテッドTV(CTV)の普及で“テレビ画面でネット動画を見る”行為が生活の標準に近づいています。大画面での集中視聴は、長尺作品やスポーツ・音楽ライブに適合。若年層ほど視聴環境が整備され、リビング回帰の動きがじわりと広がっています。これは、放送と配信の境界を曖昧にし、「番組の居場所はスクリーンに依存しない」というZ世代の感覚を後押しします。【図解:デバイス横断の視聴行動(概念)】
スマホ ──短尺・発見・個視聴
PC ───作業併用・情報探索
CTV ───長尺・没入・同時視聴
解説:若年も“長尺はリビング”という選択が増加。視聴の棲み分けが鮮明。ニュースはSNS、番組は配信で補完──情報の入口が分散する
若年層は、ニュースの一次発見をSNSやポータルで行い、必要に応じてテレビニュースのクリップや特集で“深掘り”する流れが一般的です。重要なのは、ニュースの入口が分散しても「テレビの編集価値」自体は引き続き評価されている点です。要約と配信で“入口をつくり”、テレビの分析・現場映像で“納得を与える”。この役割分担が、ニュースの受け取り方を最適化しています。【図解:ニュース消費の分業(概念)】
SNS速報 → 要約記事 → テレビ特集 → 配信アーカイブ
↑———————————回遊———————————↑
要点:入口はSNS、納得はテレビ、復習は配信。広告は「見られる設計」を起点に──完視聴前提のAVODとSNS拡散の連動
若年リーチ戦略において、見逃し配信の広告枠は“見られる確度の高い在庫”として機能します。スキップ不可・番組内挿入・音声付き再生の三点が揃うAVODは、完視聴率9割超というメディア構造的優位を持ちます。その一方で、SNSは“共感と自走拡散”に強く、動画広告を短尺クリエイティブで分解して多段露出するのが効果的です。すなわち、AVODで確実に届かせ、SNSで広げ、検索やブランドサイトで刈り取る──ファネルを横断連結するのが勝ち筋です。【図解:若年向け広告ファネル(概念)】
AVOD(完視聴)→ 検索・直来 → サイト体験
↘
SNS短尺(拡散)→ 指名検索・再訪
ポイント:確実到達×自走拡散×指名強化で面と線を一体化。“ながら”と“タイパ”に勝つ番組設計──倍速・要約・ハイライトの三層構造
Z世代の視聴様式は、ながら視聴、倍速視聴、要点視聴の三層が並立します。情報系では要約と結論を、エンタメでは見どころと名台詞を、スポーツではハイライトとスタッツを、先回りして提示する構造が必須。フル尺の“体験価値”を損なわず、要約・ハイライトで“入口価値”を最大化し、倍速でも理解が落ちない編集を施す。これが、タイパ志向の時代に番組が選ばれる条件です。【図解:三層編集の考え方(概念)】
要約(30秒)→ 結論・見どころ提示
ハイライト(3分)→ 名場面・重要箇所
フル(30〜60分)→ 体験・余韻・文脈
設計:短・中・長の3レイヤーを事前設計し、導線を相互に張る。編成・配信・宣伝が一体化するときの“勝ちパターン”
いま求められるのは、編成と配信と宣伝をひとつのダッシュボードで運用することです。編成は“どの話数で一番火がつくか”、配信は“どのクリップが最も保存されるか”、宣伝は“どの文言が指名検索を押し上げるか”。この三つの仮説を同じ指標群で検証し、翌週の台本・予告・サムネに反映させる。つまり、番組はON AIRで完成するのではなく、配信・SNS運用によって“翌週に向けてアップデートされる”プロダクトです。【図解:勝ちパターン運用フロー(概念)】
台本/編集 → 予告/切り抜き → 放送 → 配信/TVer → SNS増幅 → 指名検索上昇
←─────────────── ダッシュボード学習 ───────────────→
要:一元指標(保存・完視聴・指名)で翌週に反映。スポンサーの意思決定を変える“CTV×放送”の計測アップデート
CTV上の広告接触をテレビパネルで測定する新サービスの登場により、地上波・BS・配信の横断評価が具体的に進みます。放送CMと同一素材のCTV露出、あるいはCTV独自素材の接触まで、同一の視聴母集団で可視化されることで、テレビと配信の“重なり”と“増分”が同じ言語で語れるようになる。これは、若年リーチの実効性を数値で説明するうえで大きな武器になります。【図解:横断計測の全体像(概念)】
地上波CM ─┐
├→ 同一パネルでの広告接触統合 → 到達(重複/純増)可視化
CTV広告 ───┘
効果:テレビ×配信の真の合成効果を同じ物差しで説明可能に。この半年で起こること──ライブと参加型が若年をもう一度リビングへ連れ戻す
スポーツ、音楽、選挙、災害報道──“同時性が価値そのもの”の領域は、Z世代においてもライブの重要性を再確認させます。リビングの大画面で家族・友人と視聴しながら、縦画面のSNSで“もう一つのスタジアム”に参加する。マルチスクリーンの参加型体験は、リアルタイムの価値を再定義します。そして、ライブが終わった瞬間から、要約・ハイライト・リプレイが回り、見逃しが追いつき、次の試合や次の回に熱がつながる。“同時性×反復性”の連鎖が、若年のテレビ視聴を持続させます。【図解:ライブ再評価のメカニズム(概念)】
ライブ視聴 → SNS同時参加 → 配信ハイライト → 次回視聴予約
循環:同時性が熱を生み、配信が熱を保温する。
当社では、AI超特化型・自立進化広告運用マシン「NovaSphere」を提供しています。もしこの記事を読んで
・理屈はわかったけど自社でやるとなると不安
・自社のアカウントや商品でオーダーメイドでやっておいてほしい
・記事に書いてない問題点が発生している
・記事を読んでもよくわからなかった
など思った方は、ぜひ下記のページをご覧ください。手っ取り早く解消しましょう
▼AI超特化型・自立進化広告運用マシンNovaSphere▼

![デジマラボ [Digima Labo] by NpvaSphere(旧チャンキョメ)](https://digima-labo.com/wp-content/uploads/2023/06/logo_dezimalabo_2212763.png)