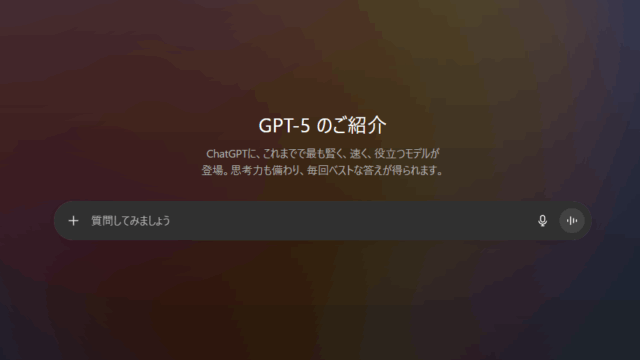ぶっちゃけ「知識」が必要なのではなく、今すぐ結果が欲しい!という方へ
宣伝失礼しました。本編に移ります。
2025年、若手のキャリア観に決定的な変化が生じました。日本能率協会の新入社員意識調査で、「定年まで1つの会社に勤めたい」という志向が約7割へと伸長しました。いわゆる「転職ありき」の神話は、少なくとも新卒段階では現実に合致しなくなっています。本稿では、なぜいまZ世代が安定を選び、しかも単なる保守回帰ではなく「副業」「専門性」「心理的安全性」と両立させる新しいリアリズムを示しているのかを、最新データと現場感覚を統合して読み解きます。併せて、企業がこの変化を機会に転じ、定着率と生産性を同時に引き上げるための実務手順を提示します。
すなわち、「会社に残る条件が満たされるなら残りたい」という意味での安定志向が強化され、裏返せば「残す条件を設計できない企業は人材を失う」というシビアな競争環境に突入した、と読むべきです。

何が起きたのか:JMA調査が示した「定年まで1社」志向の跳ね上がり
日本能率協会による2025年度の調査では、「定年まで1つの会社に勤めたい」が約7割、「1つの仕事を長く続けて専門性を磨きたい」も約7割に達しました。同時に「副業・兼業をやってみたい」は5割超、「プライベートを優先したい」は8割超。数値が示すのは、単なる保守化ではなく、生活の安定、専門性の蓄積、そして社外でのポートフォリオづくりを同時に志向するバランス感覚です。図1 2025年新入社員の主な志向(%)
プライベート優先 83.4|███████████████████████████████████████
定年まで1社 68.6|███████████████████████████████
専門性を磨きたい 67.9|██████████████████████████████
副業・兼業したい 52.8|███████████████████████
凡例:棒の長さは概数。各項目は合計100ではありません。
出典:日本能率協会 新入社員意識調査(2025年)数字が割れる理由:東商の「定年まで24.4%」とどう整合するのか
東京商工会議所の同年調査では「就職先の会社でいつまで働きたいか」の設問に対し、「定年まで」は24.4%でした。JMAの「定年まで一つの会社に勤めたい(価値観)」と、東商の「どのくらい働くつもりか(行動意図)」は、設問の趣旨も対象母集団も異なります。前者は志向性、後者は具体的な計画。加えて前者はJMA研修参加者、後者は東商研修の受講者で、業種構成も異なります。サンプルの性質が違えば、数値が違って当然です。重要なのは、「長く働きたい志向」が高い一方で、「状況が悪ければ転職も辞さない」という現実主義が併存している点です。| 指標 | JMA | 東京商工会議所 |
|---|---|---|
| 設問の軸 | 価値観(近い/どちらかというと近い) | 行動意図(単一回答) |
| 主な対象 | JMA公開教育セミナー参加の新入社員 | 東商研修受講の新入社員 |
| 「定年まで1社」等価指標 | 合計で約7割 | 24.4% |
| 補足 | 副業志向5割超、WLB志向8割超 | 「チャンスがあれば転職」25.7% |
Z世代が求める「安定」の再定義:心理的安全性、専門性、越境の三位一体
Z世代にとっての安定は、給与や企業規模だけでは完結しません。彼らが「長くいたい」と感じるのは、心理的安全性が担保され、専門性を磨くルートが見え、必要に応じて越境(副業や社内外プロジェクト)できる環境があるときです。理想の上司像としては、耳を傾け、丁寧に指導し、よい行動を具体的に称えるタイプが上位に並びます。管理の厳しさではなく、学習と挑戦を支援する関わりが鍵です。図2 Z世代の「安定」三角形
〔越境(副業・社外経験)〕
▲
/\
/ \
/ \
/ \
〔心理的安全性〕———〔専門性の成長ルート〕
ポイント:三要素が同時に満たされる領域が、長期定着と高い貢献が重なる最適点。
マクロの追い風:賃上げ常態化と政策の転換が若手の現実解を後押し
2025年の春季労使交渉は賃上げ率が2年連続で5%超に達し、最低賃金も引き上げ基調が続いています。政府も実質賃金のプラス転化を強調し、賃上げを成長戦略の要と位置づける方針を明確にしています。さらに、リスキリング投資や人的資本強化の施策が拡充され、社内で学び直しながら成長できる環境整備が加速しています。Z世代が抱く「会社で力を蓄えながらも外にも開く」という戦略を、制度面から後押しする地合いが整いつつあります。図3 賃上げと政策のモメンタム(概念図)
2024 賃上げ率 5%台|█████████
2025 賃上げ率 5%超|█████████
最低賃金 引き上げ基調→
政策 賃上げ重視・人的投資拡充→
解釈:家計の不安が和らぐほど、Z世代の「社内で実力を付ける→副業で越境」の現実解が取りやすくなる。
企業への示唆:若手が残るのは「居心地」ではなく「伸び代」と「納得感」
「残る理由」は好遇だけでは長続きしません。Z世代が重視するのは、努力が正当に評価される透明性、学習が成果につながる実感、そして人間関係のストレスが低いこと。以下の五つを制度と運用で一体化することが、最短距離の解です。 一つ目は、評価の可視化です。職務ごとに定義した成果物や行動基準に対し、評価会議のプロセスと配点ロジックを開示し、面談で「何ができれば次のレンジか」を言語化します。二つ目は、挑戦機会の設計です。新規PJへのローテーション、公募制、越境学習の支援枠を用意し、挑戦の後ろ盾を作ります。三つ目は、心理的安全性の運用です。1on1を「雑談」ではなく「合意形成のためのレビュー」に変え、承認と修正の両輪で進捗を動かします。四つ目は、働き方の柔軟性を成果につなげるマネジメントです。可視化された目標と稼働状況をもとに、時間ではなく価値でマネジメントします。五つ目は、報酬と成長の連動です。スキル認定と一体化した昇給の仕組みを整え、学びが収益貢献に直結する設計にします。図4 「残る理由」を設計する実務フロー
[ジョブ定義の透明化]→[評価会議の開示]→[1on1で次のレンジ条件を合意]
↓
[挑戦機会の供給(公募・ローテ・副業連携)]
↓
[スキル認定と報酬レンジの連動]→[定着率・生産性の改善]
内定から1年の設計図:離職の谷を越えるオンボーディング
離職が集中しやすいのは入社3カ月、6カ月、1年の節目です。ここを越えるためのオンボーディングは、単発研修ではなく「仕事の再現性を高めるメニュー×支援者×評価の同期」が肝要です。以下は、現実的に運用できる一年の雛形です。図5 新入社員オンボーディングの一年(雛形)
入社前 仕事の基礎スキル事前学習、配属先の仕事カタログ共有
0~30日 日次のミニゴール設定、1on1週1回、メンター伴走
31~90日 小さな本番任務を完遂、フィードバック→再挑戦
91~180日 部門横断のミニPJに参加、顧客接点を持つ
181~365日 専門ミッションへアサイン、成果発表と次年度目標合意
評価連動 四半期ごとにスキル認定→昇給・手当連動(透明)
見落としがちなリスク:キャリア未設計の増加と「様子見」転職予備軍
JMA調査では、将来のキャリアを「描いている」が前年から10ポイント減少し、約半数となりました。これは、将来設計を先送りする若手が増えているサインでもあります。さらに、学生・若手の層では「3年以内に転職する可能性は低い」と断言しない「様子見」群が大きな塊を形成しており、入社後の環境次第で一気に流出するリスクが潜みます。だからこそ、早期に「この会社で伸びる筋道」を可視化し、当人と合意することが何よりの離職予防になります。図6 リスクマトリクス(簡易)
発生確率
低 中 高
影 低 安 警 要
響 中 警 重要 重要
度 高 要 重要 臨
例:キャリア未設計の増加=発生確率「中」、影響度「高」→重要領域
様子見転職予備軍の存在=発生確率「中~高」、影響度「中~高」→重要~臨界
対応:入社三カ月以内にキャリア仮説を共創し、四半期単位で見直す。
ケースで考える:現場の五つの打ち手とメトリクス
一、現場長に「一人ひとりの伸び代マップ」を提出してもらい、評価会議で検証する。二、部門横断の越境PJを四半期ごとに一本立ち上げ、若手を必ず混ぜる。三、1on1では「承認→課題→次アクション→リソース」の順で言語化する。四、挑戦の失敗は「修正学習の素材」として全体共有し、称賛の文化をつくる。五、スキル認定の基準を公開し、昇給と連動させる。これらを動かすKPIは、定着率、90日生産性、1on1満足度、越境参加率、内部異動の応募数です。図7 メトリクスの見取り図(四半期レビュー)
定着率 [目標]前年同期+5ポイント
90日生産性 [目標]基準タスクの完遂率80以上
1on1満足度 [目標]平均4.2以上(5段階)
越境参加率 [目標]若手の30以上が何らかの越境に参加
内部公募応募数 [目標]毎四半期で応募件数の増加傾向維持
世代比較と就活段階の安定志向:学生期から「安定」がトップ指標
就活段階のデータでも、安定志向の強さは一貫しています。2026年卒の大学生では、企業選択のポイントとして「安定している会社」が初めて5割を超え、7年連続で最多となりました。大手志向か中小志向かの二項対立ではなく、「安定していること」を最上位に置きつつ、仕事内容や学びの質を重ね合わせて選ぶという意思決定が、学生期から既に確立しているのです。したがって、採用戦線で勝つには、待遇の提示だけでなく、入社後の「学びの設計図」を同列で提示することが不可欠です。図8 学生期の企業選択ポイント(上位)
安定している会社 51.9|████████████████████████
給料の良い会社 25.2|███████████
自分のやりたい仕事 28前後|████████████
解釈:安定が土台、その上に仕事の魅力や報酬が積み上がる構造。
採用広報を刷新する:メッセージと体験デザインの具体例
採用広報が伝えるべきは「働きがい」だけではありません。Z世代が知りたいのは「どう伸びて、何を任され、どう評価されるか」という因果のロードマップです。以下は、採用サイトや説明会スライドで即使用できるメッセージ例です。図9 コピーと体験デザイン(抜粋)
メッセージ:あなたの一年後を、今日から設計します。
要素:配属後90日の学習地図、挑戦PJの公募枠、スキル認定と昇給の連動表
メッセージ:挑戦に安全ネットを。挑戦と称賛が循環する職場へ。
要素:1on1の運用標準、失敗共有の場の設計、称賛のルール
メッセージ:越境はキャリアの保険。副業も社内起業も、道は一つではありません。
要素:副業申請フロー、社内副業の事例、社外学習の費用補助
グローバル志向の再構築:海外転勤には慎重、国内での成長機会を厚く
最新データでは、海外転勤の受け入れに前向きな層は4割程度にとどまり、前年より低下しました。一方で国内転勤の受け入れは7割弱と高水準を維持しています。Z世代は「世界に開くこと」自体を拒むわけではありません。生活基盤やコミュニティへの影響を考慮しつつ、国内にいながらグローバル案件に関わるなど、学びと貢献のバランスを取る選択を志向しています。企業は、国内で国際業務に触れられるプロジェクト設計や、短期出張型の越境機会を増やすなど、多様なルートを用意するべきです。図11 グローバル経験の新ルート(例)
国内拠点(在宅含む)→ 国際案件の共同実務 → 短期出張 → 中期派遣 → 長期赴任
始点を国内に置き、学びと生活の両立を支援するステップ設計が鍵。
総括:長く働くことは目的ではなく手段。勝者は「残る理由」をデザインできる
Z世代の変化は、企業にとって朗報です。最初から短期離職を前提とするのではなく、「続けたい」という意思を持って入社してくる。あとは企業の番です。心理的安全性、成長機会、評価と報酬の納得、柔軟な働き方、越境の機会。これらを連動させて初めて、「ここにいたい」という感情が生まれます。長く働くこと自体は目的ではありません。個と組織の成長を加速させるための強力な手段です。いま、求められているのは、若手のリアリズムに合わせて人事と現場を再設計し、「残る理由」をシステマティックに積み上げる実装力です。変化を機会に変える企業だけが、次の五年を制します。図10 要点まとめ(チェックリスト)
評価の透明性 実装済 準備中 未着手
挑戦機会(公募・越境) 実装済 準備中 未着手
1on1の運用標準 実装済 準備中 未着手
スキル認定と昇給連動 実装済 準備中 未着手
採用広報の体験提示 実装済 準備中 未着手
実務の穴を一つずつ塞いだ組織から、Z世代は自然に残り始めます。
当社では、AI超特化型・自立進化広告運用マシン「NovaSphere」を提供しています。もしこの記事を読んで
・理屈はわかったけど自社でやるとなると不安
・自社のアカウントや商品でオーダーメイドでやっておいてほしい
・記事に書いてない問題点が発生している
・記事を読んでもよくわからなかった
など思った方は、ぜひ下記のページをご覧ください。手っ取り早く解消しましょう
▼AI超特化型・自立進化広告運用マシンNovaSphere▼

![デジマラボ [Digima Labo] by NpvaSphere(旧チャンキョメ)](https://digima-labo.com/wp-content/uploads/2023/06/logo_dezimalabo_2212763.png)