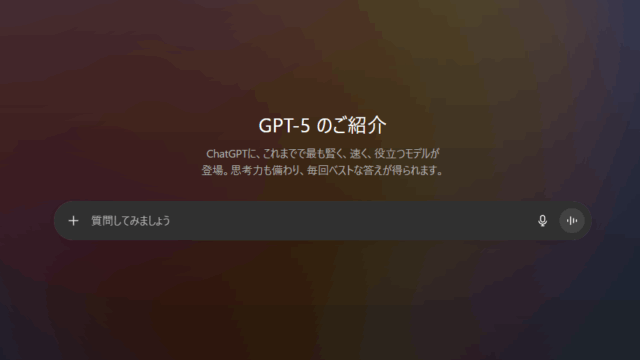ぶっちゃけ「知識」が必要なのではなく、今すぐ結果が欲しい!という方へ
宣伝失礼しました。本編に移ります。
国内有数の“行列ができない”会計体験を志したユニクロの独自決済「UNIQLO Pay(ユニクロペイ)」が、スタートからおよそ5年で静かに幕を下ろします。2025年9月下旬から登録関連機能を段階的に停止し、2026年1月に決済機能を順次停止、同月末で完全終了。ニュース自体はひと言で片づきますが、実際の現場では「会計導線」「アプリ活用」「顧客体験」「販促設計」の4点でジワリと影響が広がります。本稿では、発表内容を事実ベースで素早く整理しつつ、なぜ今なのか、ユニクロは何を捨て、どこに資源を振り向けるのかを、経営と現場の両目線で掘り下げます。業界全体で進む独自ペイの淘汰と収れん、その先にある“協調の時代”まで見通し、明日から現場で使えるチェックリストまで一気通貫でご案内します。
ここで押さえるべきは3点です。第一に、ユニクロペイは「チャージ残高型」ではなくカード/口座直結型のため、払い戻し手続きは不要です。第二に、過去の購入履歴は引き続きアプリから確認可能です。第三に、登録済みのカード番号など決済データは返品返金の受付期間が過ぎたタイミングで一括削除されます。実務としては、アプリ更新のタイミングでユニクロペイの表示や選択肢が消えるため、レジでの声かけ(「PayPayで」「カードで」など)に戻る——この運用感さえ共有できれば、大きな混乱は起きません。
現場での運用はシンプルに「アクションが1→2に戻る」だけです。ユニクロアプリ自体の役割(会員証・クーポン・在庫連携・オンラインと店舗のシームレス連携)は継続し、購入履歴の閲覧も従来どおり。顧客の所要時間はわずかに伸びますが、非接触決済や大手QRの普及で決済そのものは高速化しており、体験全体の体感差は限定的です。店舗側は、セルフレジでの声かけフローを再確認し、混雑時間帯の誘導アナウンスやサイン表示を小さくチューニングすれば十分。迷ったお客様への一次案内用に「主要対応決済一覧」をレジに掲示しておくと、現場の心理的負荷がぐっと下がります。
対照的なのは、独自ペイを会員制度と一体運用し続ける無印良品のスタンスと、当初から外部決済全面受け入れで設計してきたGUの割り切りです。いずれも「顧客体験の核にどこまで自社決済を置くか」の思想の違いから生まれた戦略といえます。ユニクロは今回、独自決済という“歯車”を外し、アプリ基盤と外部決済エコシステムを結ぶ“ハブ”としての役割を強化する側へ明確に舵を切りました。

まず事実関係:終了スケジュールと「何が」「いつ」使えなくなるのか
| 時期 | 内容 | ユーザー側の実務影響 |
|---|---|---|
| 2025年9月30日〜10月14日 | 新規会員登録/支払い方法の登録・変更を順次停止(クレジットカードの新規登録は既に停止) | 新規導入・切替はできなくなる。既存設定はこの期間も通常利用可能。 |
| 2026年1月15日〜1月29日 | ユニクロペイの決済機能を順次停止 | 順次“決済選択肢”から消える。以後は他の決済手段を選択。 |
| 2026年1月末 | サービス完全終了 | 購入履歴はアプリで確認可。チャージ残高型ではないため返金手続きは不要。登録の決済情報は所定期間経過後に一括削除。 |
ユニクロペイとは:会員提示と決済を「ひと手で」束ねる構想の全貌
[ユーザー体験フロー図]
アプリ起動→会員証QR提示→(同時に決済)→レシート発行→購入履歴に自動反映
従来)会員証提示+別アプリ/カード決済(2アクション)
UNIQLO Pay)会員証提示=決済(1アクション化)なぜ終わるのか:市場の成熟とユーザー選好の「収れん」
[簡易ヒートマップ:ユーザーが日常で選ぶ決済の重み]
クレカ(接触/タッチ/ウォレット連携)■■■■■■■■
巨大QR(PayPay等)■■■■■■■
交通系IC/非接触電子マネー■■■■■
小規模・独自ペイ■■
→ 決済は「少数の巨大エコシステム」へ収れん。店舗専用ペイの選好は相対的に低下。店舗運用のリアル:明日から現場は何を変え、何を変えないのか
[Before]
・会員QR提示=決済完了(1アクション)
・セルフレジでの滞留が少ない
・レシートと会員紐づけが自動的に完了[After]
・会員QR提示+決済手段選択(2アクション)
・「PayPayで」「カードで」の声かけ復活
・履歴紐づけは会員提示で維持競合と比較する:独自ペイを「続ける」無印良品、はじめから「持たない」GU
| 企業 | 独自ペイの有無 | 特徴 | いま見える戦略的意図 |
|---|---|---|---|
| 無印良品 | あり(MUJI passport Pay) | 会員証と決済を統合し、マイル/ポイント施策と密に連動。COIN+など低コスト基盤を採用。 | 「自社ファンの囲い込み」を軸に、外部QRも併用するハイブリッド。 |
| GU | なし(ユニクロ同様、外部決済を広範に受入。過去にはユニクロペイを店舗で利用可能に) | 自社開発コストを抑え、普及済みインフラに全面寄り添う。 | プロモ連携の自由度を重視。決済は“使い慣れたものを”。 |
| セブン-イレブン | 撤退(7pay) | 不正利用問題で短期廃止。以降は外部決済の受入拡充へ。 | セキュリティ/運用負荷の教訓。プラットフォーム連携へ回帰。 |
経営の論点:コスト構造とリスク、そして「選択と集中」
[資源配分の再設計(イメージ)]
開発/保守/セキュリティ(決済) → ▼縮小
UX改善/在庫連携/リコメンド → ▲強化
外部決済との協業(販促/CRM) → ▲強化レジ前で困らないために:ユーザー視点のミニマム対策
[現場フロー簡易チェック]
① 会員QRを見せる(これは今後も同じ)
② 決済手段を口頭で伝える(PayPay/カード/非接触等)
③ クーポン適用の有無を確認
④ レシート受取/電子領収書の要否独自ペイ淘汰の帰結:勝ち筋は「自社経済圏」か「協業の巧みさ」か
[二極化の図]
A:自社経済圏型(会員・決済・ポイントを強固に縛る)
B:協業最適化型(外部決済×自社アプリ×販促で体験最大化)
→ 市場はAとBの両極へ。汎用決済の圧倒的便利さの前で、「自前ペイを持つ必然性」の再定義が進む。現場と本部のToDo:今日からできる実務チェックリスト
[実務チェックフロー]
本部:店頭サイン更新→FAQ統一→アプリ内導線の文言更新
店舗:ピーク時案内の定型化→主要決済の可否一覧を掲示
CS:返品/返金の案内テンプレ更新→登録情報削除の説明統一
販促:大手決済との共同キャンペーン企画(会員紐づけ前提)タイムラインで振り返る:ユニクロペイの5年
[タイムライン]
2021.01 UNIQLO Pay開始(会員証×決済の一体化)
2021.09 GU店舗でも利用可能に(グループ横断の運用へ)
202x〜 登録銀行拡充/オンライン展開
2025.09 サービス終了を発表
2025.09末〜10.14 新規登録/支払方法変更を順次停止
2026.01.15〜29 決済機能を順次停止
2026.01末 完全終了(履歴は閲覧可/決済情報は後日一括削除)未来予測:2026年以降のキャッシュレス地図と、ユニクロの勝ち筋
[2026年の地図(概念図)]
「会員アプリ」=体験のハブ
「外部決済」=会計の標準装置
「販促」=両者を橋渡しする接着剤
→ 接着剤が強いほど、体験はするすると滑らかに。総括:これは「撤退」ではなく、勝つための“減らす決断”
[一言要約]
独自ペイを外したぶん、顧客体験の本丸に資源を寄せる。
決済は選べるほど良いが、体験の核は一つでいい。
当社では、AI超特化型・自立進化広告運用マシン「NovaSphere」を提供しています。もしこの記事を読んで
・理屈はわかったけど自社でやるとなると不安
・自社のアカウントや商品でオーダーメイドでやっておいてほしい
・記事に書いてない問題点が発生している
・記事を読んでもよくわからなかった
など思った方は、ぜひ下記のページをご覧ください。手っ取り早く解消しましょう
▼AI超特化型・自立進化広告運用マシンNovaSphere▼

![デジマラボ [Digima Labo] by NpvaSphere(旧チャンキョメ)](https://digima-labo.com/wp-content/uploads/2023/06/logo_dezimalabo_2212763.png)