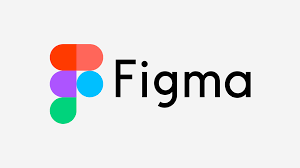宣伝失礼しました。本編に移ります。
いま、何が起きているのか——安心のはずの代引きが攻撃の踏み台に
ネット通販の「代金引換(代引き)配達」で、偽物や粗悪品が届くトラブルが全国で増えています。国民生活センターは2025年8月20日付で、代引きを利用したインターネット通販に関する注意喚起を公表しました。2019年度から2024年度にかけて、関連相談は約2.5倍に増加。2025年度は6月末時点で既に4,498件に達し、前年同期比で急拡大の様相です(出典:国民生活センター 報道発表資料)。
この動きを受け、専門メディア各紙も一斉に報道。数字と具体例を提示しながら、「代引きだから安心」という思い込みこそ最大の盲点だと繰り返し伝えています(参考:Web担当者Forum、INTERNET Watch、ケータイ Watch)。
数字が語る危機の輪郭——5年で約2.5倍、相談の半数超が「偽物」「連絡不能」
国民生活センターの図表(PIO-NET集計)から、以下の構図が読み取れます(出典:同・報道発表資料)。
- 2019年度:5,623件
- 2024年度:14,013件(5年間で約2.5倍)
- 「偽物・連絡不能」に関する相談割合:52.5%(前年から上昇)
- 「外国が関係する相談」割合:26.3%(前年から上昇)
- 2025年度(6月末時点):4,498件(急ピッチで増勢)
単純な「未着」よりも、受け取り後に判明する品質・表示の齟齬(偽物・粗悪品・素材表記の不一致)や、販売主体の所在不明・連絡不能、さらに越境事業者の関与へと質が変貌しています。支払いが受け取り時点で完了する代引きの特性が、詐欺的スキームにとって資金回収の確実性を高める“構造的な追い風”になっているのが現実です。
なぜ「代引き」が狙われるのか——心理とプロセスの死角
代引きは、①前払い未着リスクの回避、②カード情報の不提供、といったメリットから“安全”イメージが強く、心理的なハードルが低い決済です。ところが実際のフローは「受領と同時に支払う → 開封して中身を確認」の順番であり、真贋や品質の検証は支払い後に後ずれします。結果、偽物・粗悪品でも代金がすでに回収済みという構造的逆転が起き、販売サイトと連絡が取れない場合には返金ルートが消滅します(出典:国民生活センター)。
現場で確認されている主な手口
手口1:SNS・ディスプレイ広告で偽サイトへ誘導
実在するメーカーやブランドのロゴ・商品写真を無断使用し、「公式」「在庫処分」「二点目大幅割引」など過剰な訴求で関心を引きます。遷移先サイトは一見整然としていても、特定商取引法の表示(事業者名・所在地・電話番号)が曖昧、最終確認画面が出ない、といった法令不適合の兆候が頻出します。決済は代引きのみ、または注文後に一方的に代引きへ変更する例も報告されています(出典:Web担当者Forum、国民生活センター)。
手口2:注文品と異なる中身——偽物・素材違い・別物
「国産と表示されていた食品が実は外国製」「綿麻表示のはずがポリエステル100%」「有名ブランドの衣料・スニーカーが明らかな模造品」など、中身が違うケースが多数。連絡手段はメッセンジャーのみ、返信は「二割返金でどうか」「返品には高額手数料」などの揺さぶり、最終的に連絡断絶というパターンが典型です(出典:同・事例集)。
手口3:同額すり替え型の“送り付け”
報道では、「注文したスキャナーやHDDが届かない一方で、ほぼ同額のイヤホンが代引きで届いた」といった証言が取り上げられています。大量発注や多忙な現場のタイミングを突き、金額の既視感で受領を通過させる発想です(参考:FNNプライムオンライン)。送り状の差出人は「交換センター」など一般名詞、依頼主情報は曖昧で、追跡しても実体に接続できないケースが見られます(出典:国民生活センター 事例5)。
法令と構造の盲点——「表示義務」「最終確認画面」「取消し」の観点
特定商取引法は、通信販売の広告に事業者の氏名(名称)・住所・電話番号・支払時期と方法・引渡時期・申込み撤回や解除の条件等の表示を義務付けています。さらにインターネット取引では、最終確認画面に価格・分量・支払方法・引渡時期などの表示が必要で、虚偽や誤認を招く表示による申込みは取消し得る旨が規定されています(出典:同・解説部)。
しかし実務上、販売主体が越境・無連絡の場合、返金の執行は困難です。宅配事業者は配達・集金の受託者であって販売主体ではないため、販売サイトの問題を理由に返金・補償を求めることは難しいのが現状です(出典:INTERNET Watch、国民生活センター)。このギャップが、「回収より予防」を強く要請しています。
個人が今日から実行できる“防御の型”
一次審査(購入前の30秒)
- 特商法表示:事業者名・所在地・電話番号の有無と実在性を確認(地図で住所照合)。
- 最終確認画面:価格・分量・支払方法・引渡・返品条件の表示があるか。
- 言語・規約:日本語が不自然、返品・返金条件が抽象的なら離脱。
- 決済:代引き限定や注文後の一方的な代引き変更は大警戒。
- 価格:相場とかけ離れた値引き、「二点目半額」など過剰訴求は要注意。
二次審査(受け取り現場の5秒)
- 差出人・依頼主名義は販売サイト名と一致しているか。
- 伝票の品名は具体的か(汎用名・空欄は警戒)。
- 注文履歴の金額と品目名が一致しているか(金額だけの一致は罠)。
- 一つでも曖昧なら支払い前に受取保留を宣言し照合。
不審・被害時の初動
- スクショ・写真で証跡化(広告・商品ページ・注文確認・ラベル・梱包)。
- 消費生活センターまたは消費者ホットライン「188(いやや)」へ即相談。
- 販売主体が国内で法令不適合の疑いが強ければ所管への情報提供を検討。
- 偽ブランドの蓋然性が高い場合は商標権者・警察相談窓口にも連絡。
組織・店舗での“受け取りガバナンス”
オフィスや店舗では、代引き受領者の限定・立替払いの原則禁止・週次での注文一覧共有を定例化しましょう。大型キャンペーンや新店オープンなど発注が集中する時期は、期間限定で「代引き停止ウィンドウ」を設け、請求書払いやカード決済へ代替。置き配設定は、代引き混入が起きない運用に見直します。
広報・CS・法務は、偽サイト通報窓口・正規販売チャネル一覧・注意喚起ページを常設。SNSでは季節商材やセール期に合わせて再掲、広告審査部門と連携し特商法表示の自動・目視チェックを内製化。法務は証拠保全と申入れ書式を定型化し、越境時の連絡先(プラットフォーム・決済・ホスティング・権利者)を一覧化しておきます。
チェックリスト——一項目でも該当したら撤退
- 価格が相場より不自然に安い/セールが常時表示。
- 特商法表示が空欄・画像化・曖昧。
- 最終確認画面が出ない/必要事項の記載が欠落。
- 支払い方法が代引き限定/後から一方的に代引き変更。
- 連絡先がフリーメール/QRコード画像のみ。
- 住所が曖昧・海外、電話が常時話し中。
- レビューの日本語が単調・画像に透かし消し痕。
「数字の読み方」——高止まりからの再加速
件数は2020年度に一段跳ね、その後も高止まりしたままじわじわ上昇。偽物・連絡不能は五割超、外国関与は二割台後半へ。これは日本語サイト×海外運営という偽装ドメスティックの増加や、国内の転送・仕分けを介した分業化スキームの広がりと相関します。カテゴリは衣料・靴・バッグ、季節家電、生活雑貨など「画像映え」で意思決定しやすい領域に集中。価格は一万〜三万円に収まり、“高すぎず安すぎず”で警戒心を鈍らせる設計が見えます(出典:国民生活センター)。
“玄関の5秒”“注文前の30秒”“週次の15分”が損失を止める
攻撃は、私たちの行動の隙間に入り込みます。だからこそ、玄関の5秒(伝票・差出人・金額と品名の一致を確認)、注文前の30秒(特商法表示・最終確認画面・決済手段を確認)、週次の15分(組織の注文一覧と配送予定の可視化)という小さな投資を習慣に。安心は偶然では生まれません。設計された習慣が、安心を生みます。
最後に——「支払いの手前」で勝つ
代引きは本来、前払い未着リスクを抑えるための仕組みです。しかし、「届いたのに中身が違う」という新しい被害の温床にもなり得ます。攻撃者は心理と手続の隙を突き、インフラの境界に逃げ込みます。だから、支払いが起きる手前にチェックを前倒しする——これが最も費用対効果の高い防御です。自分と組織を守るのは、情報と設計。今日からできるチェックの習慣化で、被害の連鎖を断ち切りましょう。
参考リンク(一次情報・関連記事)
- 国民生活センター「代引き配達を利用したインターネット通販のトラブルにご注意」(2025年8月20日・報道発表資料PDF)
- 国民生活センター「偽物が届くインターネット通販トラブルで“代引き配達”の利用が増加しています!!」(2023年4月26日)
- Web担当者Forum「ネット通販の『代引き配達』で偽物が届くトラブル多発!」(2025年8月26日)
- INTERNET Watch「ネット通販の代引き配達で偽物や粗悪品が届くトラブルが多発!」(2025年8月21日)
- ケータイ Watch「『代引き配達を利用したインターネット通販に注意』国民生活センター」(2025年8月25日)
- FNNプライムオンライン「勝手に“代引き”変更で偽ブランド品が…」 (2025年8月22日)
本文字数:8126
当社では、AI超特化型・自立進化広告運用マシン「NovaSphere」を提供しています。もしこの記事を読んで
・理屈はわかったけど自社でやるとなると不安
・自社のアカウントや商品でオーダーメイドでやっておいてほしい
・記事に書いてない問題点が発生している
・記事を読んでもよくわからなかった
など思った方は、ぜひ下記のページをご覧ください。手っ取り早く解消しましょう
▼AI超特化型・自立進化広告運用マシンNovaSphere▼

![デジマラボ [Digima Labo] by NpvaSphere(旧チャンキョメ)](https://digima-labo.com/wp-content/uploads/2023/06/logo_dezimalabo_2212763.png)