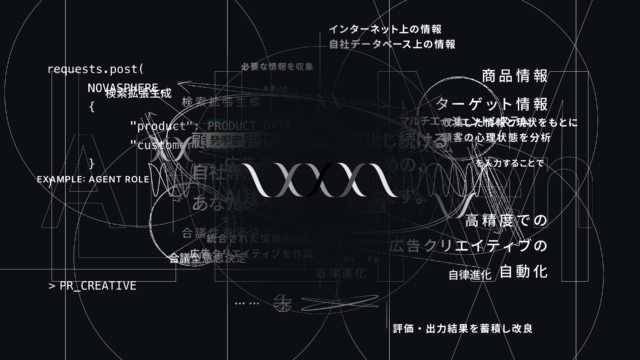宣伝失礼しました。本編に移ります。
キーワードを打ち込んで、並んだ商品から自力で絞り込む。長年、ECの当たり前だったこの行為が、いよいよ過去のものになりつつあります。2025年8月20日、KDDIグループのauコマース&ライフ(以下、auCL)は、同社が運営する「au PAY マーケット」のコンセプトページ「favomore(ファボモア)」に、対話型AIアシスタントを先行導入しました。ユーザーが自然文で相談すると、AIが適切に“聞き返し”ながら要望を解像度高く捉え、最適な商品を提案する——。検索欄の前で固まる時間は減り、店員に話しかけるように“話せば出会える”体験が、いよいよ標準機能になり始めました。
なにが起きたのか
先行導入の舞台は「favomore」。2025年4月に開設されたこのページは、生成AIなども活用し、ユーザー自身が言葉にしにくい好みや気分を汲み取って、雑誌をめくるように厳選アイテムと出会えることを狙った実験区です。今回の対話型AIは、カラクリ株式会社の顧客対応AIエージェント「Generative Navigator(GeN)」を活用したもので、“聞き返し”を前提に会話を進めるのが最大の特徴です。たとえば「友人の結婚式に着ていくワンピースが欲しい」と伝えると、テイスト、色、丈感、予算、体型の悩みなどを順にヒアリング。やり取りの中で条件が整理され、解像度の高いレコメンドにたどり着きます。auCLはこの導入で、①潜在ニーズの発見、②シーン別のパーソナル提案、③悩みに寄り添うソリューション提案、④こだわり条件によるスマート検索、⑤24時間365日の安心サポート、という5つの価値を掲げています。単なる“候補の羅列”ではなく、“いまの自分にフィットするもの”に導くコンシェルジュ体験が、モールの中に常駐するイメージです。
なぜ今、検索から対話へ
なぜ今、検索から対話へシフトするのか。背景には、生成AIの一般化と、消費者側の“探し方”の変化があります。米Amazonは2024年に買い物アシスタント「Rufus」を米国で発表し、商品選びの相談から比較、詳細Q&Aまでをチャットで一気通貫させました。国内でも2025年7月、LINEヤフーの「Yahoo!ショッピング」がβ版として“AIが最初に質問を投げかける”対話型検索を実装し、回答内容との合致度を示す「AIマッチスコア」まで提示しています。楽天も2025年7月にエージェント型AI「Rakuten AI」を本格提供し、秋には「楽天市場」への展開を予定と発表しました。中国では淘宝(Taobao)が2023年から生成AIアシスタント「問問(Wenwen)」を実装し、テキストだけでなく画像や短尺動画も織り交ぜた提案を行っています。世界の主要プレイヤーが“店員のようなAI”を標準化しつつある中で、KDDIグループの動きは日本のEC標準を塗り替える号砲と言えます。加えて、消費者側の“AI経由トラフィック”は確実に増えています。生成AI由来のサイト訪問は、この1年で桁違いに伸び、旅行や小売のカテゴリで顕著な増加が観測されています。若年層ほど“まずAIに訊く”傾向が強く、検索エンジンやSNSに加えて、会話型AIが新たな“入口”として並び立つ時代です。この“入口”でブランドの文脈が正しく伝わるかを左右するのが、会話に耐える情報の整備であり、対話UIそのものの有無です。
体験の核心:会話が意思決定コストを削る
体験の核心は、会話のスムーズさにあります。従来の検索は、キーワード→結果→再検索の反復運動でした。対話AIは、たった一文の相談から“問い直し”で要件を段階的に言語化してくれます。たとえば「在宅ワークでもオンライン会議で映えるトップス」と打ち込めば、袖丈や素材感、体温調節、洗濯のしやすさなど“本当に気にしている条件”を引き出し、候補を数点に圧縮。さらにレビューの要点やサイズ感の傾向まで一気に要約してくれるため、比較の負荷が一気に下がります。“買い物の意思決定コスト”を削るのはもちろん、対話の過程そのものが発見のきっかけになる——ここが検索との決定的な違いです。もう一つ、具体的な会話例を見てみましょう。「家族4人で初めてのキャンプ。初心者でも扱いやすいバーベキューグリルが欲しい」と入れると、AIは使用頻度、持ち運び手段、収納スペース、火起こしの経験、設置場所の制約などを順に尋ねます。ここで「車移動」「ベランダでも使いたい」「炭の扱いに自信がない」と答えれば、カセットガス式の卓上グリルを中心に、火力の目安、必要な付属品、安全に楽しむポイントまでまとめて提案。“売れているから”ではなく、“あなたの前提条件に合うから”を根拠に商品が出てくるので、納得感が段違いです。
技術の裏側:GeNとモールデータの掛け算
裏側では、LLM(大規模言語モデル)と検索・商品データが緊密に連携しています。GeNは、FAQ検索や決め打ちのシナリオで対応する従来型ボットと異なり、顧客対応の本質である「問題の特定」プロセスをAIで再現する特許技術を持ちます。AIが“答えを作る”に加え、“適切な質問を作る”ことに長け、会話の前半で要求の本質を素早くあぶり出す。この対話管理の骨格に、モールの膨大な商品属性、在庫、レビュー、ランキングといった構造化データをつなぎこむことで、“意味の分かるレコメンド”を瞬時に返せる設計です。auCLは2024年から段階的に生成AIチャットボットの導入・運用を進めており、問い合わせ領域で得た知見(語彙、口調、禁止応答、社内FAQの整備など)が今回の購買支援の会話設計にも活きています。安全性と正確性の面でも、社内ドキュメントや公式ヘルプの根拠に基づく回答を優先し、必要に応じて人のオペレーターにエスカレーションできるようにするなど、EC実務に耐えるガバナンスが敷かれています。GeNの強みは“問診力”だけではありません。会話中に生成された仮説や条件を、背後のナレッジベース・商品検索・在庫APIと即座に照合し、“根拠のある短い結論”にまとめ直す要約力にもあります。たとえばレビュー1,000件のうち、サイズに関する記述だけを抽出して「小さめ」「ちょうど」「大きめ」の比率を示す、洗濯後の縮みについて一定の傾向があるなら注意喚起を添える、といった“実用的な一行”を返せます。この“要点の抽出と再構成”は、人手ではコストが大き過ぎる領域であり、生成AIが企業運用に入る最大の価値領域の一つです。
ビジネスインパクト:CVR、LTV、広告最適化
ビジネス面のインパクトは小さくありません。第一に、比較・検討の摩擦低減は、回遊離脱を抑え、コンバージョン率(CVR)の底上げに直結します。第二に、会話から抽出される“用途・悩み・こだわり”という高解像の一次データは、従来のクリックログでは取れない金鉱です。商品開発、仕入れ、特集企画、検索条件の初期値、レビューの見せ方まで、無駄や過不足の少ないPDCAが回せます。第三に、レビュー要約や比較表の自動生成は、ECの広告・販促運用(クリエイティブの量産やABテスト)も加速させます。海外では、生成AIショッピングアシスタントの“下流効果”が売上を押し上げるとの報道も増えており、対話AIは単なるUX改善を超えて、収益設計の中心に入りつつあります。返品率の低減も見逃せません。サイズや使用方法の誤解、期待値のズレが主要因であるカテゴリほど、対話で事前に齟齬を解消できます。“購入前の会話”が“購入後の満足”の先行指標になれば、長期LTVは自然に積み上がります。また、広告投資の最適化という観点でも、会話起点のデータは強力です。どの媒体でどんな“言葉”を見た人が、最終的にどんな“言葉”で決断したのか。これまでブラックボックスだった“言語の旅路”が可視化され、クリエイティブ開発とメディアバイイングの精度が一段と上がります。
成功KPIの設計
成功の鍵は、適切なKPI設計にあります。ページ滞在時間や直帰率だけでは、会話の価値は測れません。たとえば、会話完了率(AIが提案まで到達した割合)、聞き返し解像度(2〜3往復で要件がどれだけ具体化したか)、提案採用率(提示カードからの詳細閲覧・カート投入率)、比較短縮度(ユーザー自身の再検索回数の減少)、FAQ自己解決率(配送・返品などの自己完結率)、マーチャンダイジング貢献度(会話から生まれた特集・ランキングのCVR)といった指標が有効です。さらに、会話ログから抽出した“生活文脈タグ”(季節イベント、同伴者、移動手段、体型・肌質の特徴など)を商品属性に付与し、検索やレコメンドの精度向上に還元する設計が、中長期の差を生みます。
リスクとガバナンス
もちろん課題もあります。生成AIは、未知の質問に対して流暢に“もっともらしい誤り”を返すリスクを抱えます。対策としては、①回答根拠の優先順位づけ(公式情報>店舗規約>レビュー要約の順)、②ナレッジベースとLLMのハイブリッド構成、③プロンプトガードレールと不適切表現のフィルタ、④“分からないときは聞き返す/人に繋ぐ”設計、⑤会話ログに対する定期的な人手評価、の5点が実務上の肝になります。さらに、プライバシーとパーソナライズのバランス、在庫・価格のリアルタイム性、モデル運用コストなど、運用設計の最適化も不可欠です。試行導入(パイロット)でユーザー体験と内部KPIを磨き、対象カテゴリやタッチポイントを段階的に広げるアプローチが最も合理的です。
経済圏シナジーの可能性
KDDIグループにとっては、経済圏資産とのシナジー創出も大きなテーマです。決済、ポイント、メディア、ライブ配信、サブスクといった接点に“会話”の糸を通すことで、ニーズの芽生えから購入、利用後サポートまでを一気通貫でつなげられます。たとえば、ライブコマース視聴中に「似た雰囲気で少し短めの丈のワンピースは?」とAIに尋ねれば、在庫・サイズ・クーポン情報まで咀嚼した上で、その場で提案・購入まで完結する。“広告を見る→検索する→比較する”という長い導線が、“会話する→納得する→買う”という短い導線に置き換わるほど、モール全体の体験は軽くなります。
ロードマップ
今回の先行導入は、あくまでスタートです。短期的には、「favomore」でのユースケースを水平展開し、ファッション以外の高関与カテゴリ(家電、コスメ、ベビー、家具など)へ広げるべきです。中期的には、アプリの常駐タブ化、音声入出力への対応、画像・動画を使った“見せながらの対話”、会員データに基づく“次の一手”の提案(買い替え・消耗品の自動提案)へと発展させます。長期的には、店舗・コールセンター・配送を含む全チャネルで同じ会話履歴を参照し、どこからでも続きを始められる“オムニ対話”の実現へ。さらに、出店者向けには“AI接客テンプレート”を提供し、ブランド自身がトーン&マナーを保ったまま対話接客を自走できる仕組みを整えると、モール全体の“接客密度”が一段上がります。
出店者の実務ポイント
出店者・ブランド側の実務ポイントも明確です。第一に、商品マスタの再設計。サイズ、素材、用途、相性、季節、メンテナンス、推奨シーンなど、“会話で出てくる言葉”で属性を整備しましょう。第二に、レビューの構造化。身長・体重・肌質・使用シーンなどの記述を誘導し、AIが要約しやすい土壌を作ることが重要です。第三に、比較観点の定義。ユーザーが迷う軸(価格帯、サイズ感、機能のグレード、初心者向け/上級者向け)を先に用意し、AIが躊躇なく“違い”を説明できるようにします。第四に、NG回答の明示。安全保障や医療・薬機、法令に抵触する応対は禁止ルールをプロンプトに組み込み、逸脱時は人に接続する運用を徹底します。第五に、会話データの利活用。売れ筋分析だけでなく、“買わなかった理由”の抽出こそが大きな改善源です。
競争軸の転換:AIOの時代
対話AI時代の競争軸は“表示順位”から“問診力”へと移ります。ユーザーの曖昧な要望を、どれだけ少ない往復でクリアな要件に変換できるか。ここで差がつきます。そのためには、AIO(AI最適化)を前提に、商品説明の“文脈密度”を高め、写真・動画・サイズ表・素材の実測値など、AIが引用しやすい一次情報を公開することが不可欠です。検索の上位表示に投資するだけの時代は終わり、AIが“根拠として参照したくなる情報”をどこまで提供できるかが、発見の確率を左右します。
海外事例からの学び
海外事例からも学べます。AmazonのRufusは、ユーザーが「雨の日の通勤に最適なレインシューズが欲しい」と尋ねると、滑りにくさ、重量、耐久性、レビューの代表的評価を要約して、価格帯ごとに数点を提示します。個別商品ページでは「このジャケットは洗濯機で洗える?」といった細かな疑問にも即答。“検索ではなく相談”を徹底することで、ユーザーは迷う時間を減らし、発見と決断の速度を上げています。
よくある誤解への回答
よくある誤解として、「対話AIは高度すぎて高齢層には難しいのでは」という指摘があります。実際には逆で、会話はもっとも直感的なUIです。“専門用語なしで困りごとを話せばいい”というハードルの低さは、年齢を問いません。重要なのは、選択肢の提示や言い換え提案など、読みやすい会話設計です。また、「AIが勝手に不正確な回答をしないか」という懸念については、現場オペレーションでカバーできます。根拠の明示、引用元へのリンク、重要事項の段階的な確認、最後の確定前に“これでよろしいですか?”と念押しするなど、設計と運用で事故確率は大きく下げられます。
対話AI×小売の未来図
この潮流は、2026年以降さらに広がります。対話はテキストだけでなく、画像や動画、音声、位置情報を横断する“マルチモーダル”が主戦場になります。服をカメラで映して「この色に合うネクタイを」と話しかければ、AIが画像から色味と質感を読み取り、季節やTPOに合う候補を教えてくれる。家電なら、設置予定の部屋を撮影して「このスペースに収まる、静かな除湿器」を相談すれば、幅・奥行・運転音のしきい値を自動で判定し、最適解に導く。ECの“画面に合わせる顧客”から、“顧客に合わせる画面”へ。体験設計の主語が完全に入れ替わります。
倫理・法令・ブランドの課題
一方で、倫理と法令のアップデートも並走します。生成AIが広告・販促のキャッチコピーを自動生成する局面では、誇張表現や比較広告の線引きを厳格に運用する必要があります。薬機法や景表法に抵触するリスクを回避するため、特定カテゴリではAIが生成可能な文言を“ホワイトリスト方式”で制御する、承認済み表現のライブラリを持つ、といった運用が欠かせません。ブランドトーンの一貫性も重要です。AIの口調は“店員らしさ”に直結します。呼称、敬語レベル、謝意や断り方の基準、絵文字の使用、行間の長さまで、スタイルガイドを用意して学習させるべきです。
まとめ
“検索に別れを”。KDDIグループの一手は、ECの常識を静かに塗り替え始めました。ユーザーは考えを言葉にし、AIはそれを問い直し、最適解に導く。買い物の本質は、膨大な候補から選び抜く行為ではなく、“自分に合うものに出会う旅”であることを、対話AIは思い出させてくれます。次に会話を始めるのは、あなたの番です。
参考リンク
- KDDIグループがECの買い物を“検索”から“対話”へシフト。「au PAY マーケット」に「対話型AIアシスタント」を導入(ネットショップ担当者フォーラム、2025年8月21日)
- ECのお買い物が“検索”から“対話”へ。「対話型AIアシスタント」をau PAY マーケットのコンセプトページ「favomore」に先行導入(auコマース&ライフ プレスリリース、2025年8月20日)
- auコマース&ライフ|ニュース一覧(対話型AIアシスタント先行導入、2025年8月20日掲載)
- au PAY マーケットに、顧客対応AIエージェント「GeN」の導入が決定(カラクリ ニュース)
- 「favomore(ファボモア)」とは?(ネットショップ担当者フォーラム、2025年4月3日)
- au PAY マーケット、対話型AIアシスタントをコンセプトページに先行導入(ECのミカタ、2025年8月)
- 顧客対応AIエージェント GeN(サービスページ・特許技術の記載)
- KARAKURI chatbot:ハルシネーション抑制のハイブリッド機能(PR TIMES、2023年11月1日)
- Amazon Rufus(About Amazon、2024年2月1日)
- Scaling Rufus(AWS Machine Learning Blog、2024年10月10日)
- How Rufus doubled inference speed(AWS Machine Learning Blog、2025年5月28日)
- 「Yahoo!ショッピング」アプリ、生成AIが質問を通じて商品検索をサポート(LINEヤフー プレスリリース、2025年7月2日)
- 同上のβ版機能解説記事(Web担当者Forum、2025年7月3日)
- ITmedia:生成AIとの会話で“あなたにぴったりの商品”提案(2025年7月3日)
- 楽天がエージェント型AIツール「Rakuten AI」の本格提供を開始(楽天モバイル プレスリリース、2025年7月30日)
- 楽天、エージェント型の「Rakuten AI」開始(Impress Watch、2025年7月30日)
- Alibaba:Taobao Wenwen 概要(Forrester Blog、2023年11月2日)
- 生成AI由来トラフィックの急増(Adobe Analytics Blog、2025年3月17日)
日本語文字数:5233字
当社では、AI超特化型・自立進化広告運用マシン「NovaSphere」を提供しています。もしこの記事を読んで
・理屈はわかったけど自社でやるとなると不安
・自社のアカウントや商品でオーダーメイドでやっておいてほしい
・記事に書いてない問題点が発生している
・記事を読んでもよくわからなかった
など思った方は、ぜひ下記のページをご覧ください。手っ取り早く解消しましょう
▼AI超特化型・自立進化広告運用マシンNovaSphere▼

![デジマラボ [Digima Labo] by NpvaSphere(旧チャンキョメ)](https://digima-labo.com/wp-content/uploads/2023/06/logo_dezimalabo_2212763.png)