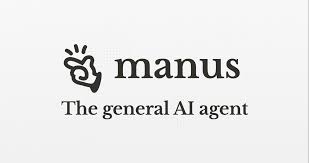宣伝失礼しました。本編に移ります。
「リターゲティング広告の成果が、最近どうも頭打ちだ」「CPA(顧客獲得単価)がなかなか下がらない」「Cookie規制の影響が不安だ」このような課題を抱えるWebマーケティング担当者の皆様へ。その停滞感を打破する鍵は、運用型広告における「リーセンシー」の最適化にあるかもしれません。リーセンシーとは、ユーザーがサイトを訪問してから経過した時間のこと。この「時間」という要素を戦略的に操ることで、無駄な広告費を徹底的に削減し、コンバージョン率を劇的に向上させることが可能です。本記事では、運用型広告のスペシャリストとして、リーセンシーの基礎知識から、明日から実践できる具体的な戦略、主要プラットフォームでの設定方法、そして避けては通れないポストCookie時代への対応策まで、全てのノウハウを網羅的に解説いたします。この記事を最後までお読みいただければ、貴社の広告パフォーマンスを次のステージへと引き上げるための、明確なロードマップが手に入ることでしょう。

運用型広告におけるリーセンシーの定義とは?フリークエンシーとの明確な違い
まず、リーセンシーという言葉の正確な定義から始めましょう。マーケティング、特に運用型広告の文脈における「リーセンシー(Recency)」とは、ユーザーが特定の行動(例えば、ウェブサイトへの訪問、商品のカート投入など)を起こしてからの「経過時間」または「間隔」を指します。リターゲティング広告において、オーディエンスリストをセグメントする際の極めて重要な軸となります。
リーセンシーとフリークエンシーの違い
リーセンシーとしばしば混同される用語に「フリークエンシー(Frequency)」があります。この二つは全く異なる概念であり、正確に使い分けることが広告運用の精度を高める第一歩です。
- リーセンシー(Recency):接触からの「経過時間」。最後に広告に接触してからどれくらいの時間が経ったか、最後にサイトを訪問してから何日が経過したか、といった「時間軸」の指標です。
- フリークエンシー(Frequency):接触「回数」。特定の期間内に、一人のユーザーが何回広告に接触したか、という「量」の指標です。
簡単に言えば、「いつ接触したか(リーセンシー)」と「何回接触したか(フリークエンシー)」の違いです。フリークエンシーの過剰な増加は「広告疲弊」を引き起こし、ユーザーに不快感を与えブランドイメージを損なうリスクがありますが、リーセンシーはユーザーの購買意欲を測るための温度計のような役割を果たします。本記事では、この「時間」の概念であるリーセンシーに焦点を当て、その戦略的な活用法を深掘りしていきます。
なぜ獲得型広告でリーセンシーがこれほどまでに重要なのか?
では、なぜこの「リーセンシー」という指標が、広告の費用対効果(ROAS)を最大化する上でこれほどまでに重要視されるのでしょうか。その理由は、ユーザーの「購買意欲」と密接に結びついているからです。ここでは、リーセンシーが重要である3つの核心的な理由を解説します。
理由1:経過時間が短いほど、ユーザーの購買意欲は高い
最も重要な原則は、「サイト訪問からの経過時間が短いユーザーほど、商品やサービスに対する興味・関心、そして購買意欲が高い状態にある」ということです。考えてみれば当然のことですが、例えば、ある商品をカートに入れたユーザーは、その直後が最も購入に近い状態にあります。しかし、1週間、1ヶ月と時間が経過するにつれて、その熱量は徐々に冷めていき、他の競合商品に目移りしたり、そもそも購入の必要性を忘れてしまったりするでしょう。このユーザーの心理状態の推移を可視化するのがリーセンシーです。意欲が最高潮に達している「ホットなユーザー」と、関心が薄れつつある「コールドなユーザー」を見分けるための、唯一無二の指標と言えます。この"熱量"の違いを無視して、全てのサイト訪問者に同じ広告を同じように配信することは、貴重な広告予算を無駄に投下していることに他なりません。
理由2:ROAS(広告費用対効果)の最大化に直結する
リーセンシーを戦略的に活用することは、ROASの最大化に直結します。前述の通り、コンバージョンに至る可能性が最も高いのは、リーセンシーが短い、つまりサイト訪問直後のユーザーです。広告運用とは、限られた予算の中でいかにしてコンバージョンを最大化させるかというゲームです。であるならば、最も成約確度の高いユーザー層に予算を集中投下し、逆に見込みの薄いユーザー層への配信を抑制するのが定石となります。リーセンシーに基づいてオーディエンスリストを「訪問後1〜3日」「4〜7日」「8〜30日」といった形でセグメントし、それぞれのリストに対して入札単価に強弱をつける。このシンプルな施策だけで、広告アカウント全体のCPAは劇的に改善し、結果としてROASは大きく向上するのです。無駄なクリックを減らし、"勝ち筋"のあるクリックを増やす。これがリーセンシー最適化の本質です。
理由3:無駄な広告配信の削減とユーザー体験の向上
リーセンシーを考慮しないリターゲティングは、時にユーザーにとって「ストーカー行為」と受け取られかねません。すでに商品を購入したユーザーにいつまでも同じ広告を表示したり、全く関心を失ったユーザーを何ヶ月も追いかけ続けたりすることは、広告費の無駄遣いであると同時に、ユーザーに「しつこい」というネガティブな印象を与え、企業のブランド価値を毀損するリスクすらあります。コンバージョン済みのユーザーや、設定した検討期間を大幅に超えたユーザーをリターゲティングの対象から「除外」する。この除外設定もまた、リーセンシー活用の重要な側面です。これにより、無駄なインプレッションやクリックを防ぎ、広告費を節約できるだけでなく、ユーザー体験を保護し、長期的な顧客との良好な関係を築くことにも繋がるのです。
明日から実践可能!リーセンシーを活用した具体的な広告配信戦略
リーセンシーの重要性をご理解いただけたところで、次に、それをどのようにして具体的な広告配信戦略に落とし込むのかを解説します。高度な分析ツールは不要です。今お使いの広告管理画面の設定を見直すだけで、大きな改善が期待できます。
戦略1:経過時間によるオーディエンスリストの分割
全ての施策の基礎となるのが、サイト訪問後の経過時間に基づいたオーディエンスリストの分割です。全てのサイト訪問者を「ひと塊」として捉えるのではなく、熱量に応じて細かく分類します。この分割の仕方は、後述する商材の検討期間によって大きく異なりますが、一般的なECサイトを例にすると、以下のような分割が考えられます。
- リストA(ゴールデンタイム):サイト訪問後 1日〜3日以内
- リストB(検討中期):サイト訪問後 4日〜7日以内
- リストC(検討後期):サイト訪問後 8日〜30日以内
- リストD(長期検討・休眠層):サイト訪問後 31日〜90日以内
このようにリストを分割することで、それぞれのセグメントに対して最適なアプローチを設計する準備が整います。
戦略2:リストに応じた入札単価の強弱調整
リストを分割したら、次に行うのが入札単価の調整です。最もコンバージョン率が高いと想定されるリストA(ゴールデンタイム)には、最も強い入札単価を設定し、広告の表示機会を最大化します。逆に、リストD(長期検討・休眠層)には入札単価を大幅に引き下げるか、場合によっては配信対象から除外することも検討します。
- リストA(1〜3日):入札単価を基準値の+50%に強化。積極的に表示を狙う。
- リストB(4〜7日):基準値通りの入札単価で配信。
- リストC(8〜30日):入札単価を基準値の-30%に抑制。機会損失を防ぐ程度に表示。
- リストD(31日〜90日):配信対象から除外、もしくは大幅に抑制。
この強弱をつけるだけで、広告費は自動的に最も確度の高いユーザー層へと最適配分されていきます。
戦略3:期間に応じたクリエイティブとオファーの出し分け
さらに一歩進んだ戦略が、リーセンシーに応じて広告クリエイティブや訴求内容(オファー)を変更することです。ユーザーの心理状態の変化に合わせて、最適なメッセージを届けることで、コンバージョン率をさらに高めることができます。
- リストA(1〜3日):最も関心が高い時期。「今なら送料無料」「本日限定クーポン」など、緊急性や限定性を訴求し、即時購入を強力に後押しする。カートに入れた商品そのものを表示するダイナミック広告も極めて有効。
- リストB(4〜7日):少し冷静になり、他社製品との比較検討を始めている可能性がある時期。商品の機能的な優位性や顧客のレビュー、導入事例などを提示し、論理的に説得するクリエイティブが効果的です。
- リストC(8〜30日):関心が薄れ始めている時期。「期間限定セールのお知らせ」や「関連の新商品」など、改めて興味を喚起するような情報を提供し、再訪を促します。
このようにユーザーの検討フェーズに合わせてコミュニケーションを変えることで、広告は「追いかける」ものから「導く」ものへと昇華します。
戦略4:CV済みユーザーと長期離脱ユーザーの除外設定
攻めの戦略と同時に重要なのが、守りの戦略である「除外設定」です。これを怠ると、広告費の垂れ流しとブランド毀損に繋がります。
- コンバージョン済みユーザーの除外:商品を購入した、あるいは問い合わせを完了したユーザーは、少なくとも短期間はその広告の対象から外すべきです。コンバージョン地点のサンクスページURLを基にリストを作成し、リターゲティングキャンペーンから除外設定します。
- 長期離脱ユーザーの除外:商材の平均的な検討期間を大幅に超えたユーザー(例:90日以上サイト訪問がないユーザー)は、配信対象から除外します。これにより、完全に見込みがなくなったユーザーへの無駄な広告配信を停止できます。
この除外設定は、CPA改善に即効性のある施策であり、必ず実施すべき基本的な設定です。
主要な広告プラットフォームでの具体的な設定手順
ここからは、Google広告、Meta広告(Facebook・Instagram)、Yahoo!広告という3つの主要プラットフォームで、リーセンシーに基づいたオーディエンスリストを作成する具体的な手順を解説します。
Google広告での設定手順
- Google広告の管理画面右上の「ツールと設定」から、「共有ライブラリ」内にある「オーディエンス マネージャー」を選択します。
- 左側のメニューから「オーディエンス リスト」をクリックし、「+」ボタンから「ウェブサイトを訪れたユーザー」を選択します。
- 「リストのメンバー」の項目で、「次のいずれかのルールに合致するページの訪問者」などを選択し、対象としたいユーザー(例:すべての訪問者、特定ページの訪問者)を定義します。
- 【最重要】「有効期間」の項目で、このリストにユーザー情報が保持される日数を設定します。これがリーセンシー期間となります。例えば「7日間」と設定すれば、「サイト訪問後7日以内のユーザーリスト」が作成されます。
- この要領で、「1日間」「7日間」「30日間」など、複数の有効期間を設定したリストをそれぞれ作成します。
- 作成したリストを各広告グループの「オーディエンス」設定でターゲットとして追加し、リストごとに入札単価調整比率を設定します。
Meta広告(Facebook・Instagram)での設定手順
- Meta広告マネージャのメニューから「すべてのツール」を開き、「オーディエンス」を選択します。
- 「オーディエンスを作成」ボタンをクリックし、「カスタムオーディエンス」を選択します。
- ソースとして「ウェブサイト」を選択し、次へ進みます。
- 対象としたいウェブサイトイベント(例:すべてのウェブサイト訪問者、特定のウェブページにアクセスした人など)を選択します。
- 【最重要】「リテンション期間」という項目に、ユーザーをオーディエンスに保持する日数を入力します。これがリーセンシー期間(最大180日)です。
- この手順を繰り返し、「リテンション期間」を「3日」「7日」「30日」など、戦略に合わせて複数パターン作成します。
- 広告セットの「オーディエンス」設定で、作成したカスタムオーディエンスをターゲットに指定、もしくは除外設定を行います。
Yahoo!広告での設定手順
- まず、サイトリターゲティング用のタグをウェブサイトの全ページに設置します。
- Yahoo!広告の管理画面上部の「ツール」から「ターゲットリスト管理」を選択します。
- 「ターゲットリストを追加」ボタンをクリックし、「条件リスト」を選択します。
- ターゲットリスト名を入力し、条件としてURLを指定します。(例:「URLが次を含む」「yourdomain.com」)
- 【最重要】「訪問履歴の有効期間」で、ユーザーの訪問履歴を保持する期間を1日から最大540日まで設定できます。これがリーセンシー期間となります。
- この手順で、期間の異なる複数のターゲットリスト(例:3日間、7日間、30日間)を作成します。
- 広告グループの「ターゲット設定」で作成したリストを紐づけ、入札価格調整率を設定して配信の強弱をコントロールします。
【CPA改善の鍵】商材・サービス別の最適なリーセンシー戦略
これまで解説してきた戦略は、全てのビジネスに画一的に適用できるわけではありません。最大の効果を得るためには、自社が扱う商材やサービスの特性、特に「購入検討期間」に合わせてリーセンシー戦略を最適化する必要があります。
高価格帯・BtoB商材(検討期間が長いケース)
自動車、不動産、高級腕時計、法人向けSaaSツールといった高価格帯・BtoB商材は、購入に至るまでの検討期間が数週間から数ヶ月、時には半年以上と長くなるのが特徴です。ユーザーは情報収集、比較検討、社内稟議など、複数のステップを経て意思決定を行います。このような商材で、訪問後数日間のユーザーにのみ集中的に広告を配信する短期決戦型のリーセンシー戦略は逆効果です。
- 最適な期間設定:リーセンシーは長めに設定するのが基本です。「30日」「60日」「90日」といった単位でリストを分割し、長期的な視点でアプローチします。
-
戦略のポイント:
- 性急なクロージングは避ける:訪問直後のユーザーに「今すぐ契約!」といった広告をぶつけるのは悪手です。まずはお役立ち資料のダウンロードやセミナーへの誘導など、ナーチャリングを目的とした中間コンバージョンを促します。
- 段階的な情報提供:リーセンシーが短い段階では「機能紹介」、中期では「導入事例・お客様の声」、後期では「競合比較資料」といったように、検討フェーズの深化に合わせて提供する情報を変化させ、継続的に接点を持ち続けることが重要です。
- ブランド想起を促す:長い検討期間の中で忘れ去られないよう、定期的にブランド名やロゴを想起させるような広告を配信し、選択肢に残り続けることを目指します。
低価格帯・消費財(検討期間が短いケース)
アパレル、コスメ、日用品、食品といった低価格帯のBtoC商材は、比較的検討期間が短く、衝動的な購入も多いのが特徴です。ユーザーの熱量が最も高い、サイト訪問直後の「ゴールデンタイム」を逃さず刈り取ることが成果を最大化する鍵となります。
- 最適な期間設定:リーセンシーは短く設定し、短期集中型のアプローチが有効です。「1日」「3日」「7日」といった短い期間でリストを区切り、メリハリの効いた配信を行います。
-
戦略のポイント:
- 初動にリソースを集中投下:サイト訪問後24時間〜72時間が最もコンバージョンしやすい期間です。この期間のオーディエンスリストには入札を最大限に強化し、クーポンや送料無料といった強力なオファーを提示して一気に購入を促します。
- カート離脱者への即時アプローチ:特に「カート放棄」したユーザーは最重要ターゲットです。カート離脱後1時間以内に「お買い忘れはありませんか?」といったリマインド広告を配信する設定は非常に効果的です。
- 購入サイクルを考慮する:化粧品やサプリメントのような定期的な購入が見込める消耗品の場合、「前回購入から30日後のユーザー」といったリストを作成し、リピート購入を促す広告を配信するリーセンシー戦略も有効です。これは顧客LTV(生涯価値)の向上に直結します。
効果測定と最適化の方法論:A/Bテストで「勝ちパターン」を見つける
リーセンシー戦略は、一度設定して終わりではありません。ビジネス環境やユーザーの行動は常に変化するため、継続的な効果測定と改善が不可欠です。そのための最も強力な手法が「A/Bテスト」です。
A/Bテストの設計と実施
A/Bテストとは、特定の要素だけが異なる2つ以上のパターン(AとB)を用意し、どちらがより高い成果を出すかを実際に配信して検証する手法です。リーセンシー戦略においては、以下のようなテストが考えられます。
- 期間設定のテスト:「訪問後7日以内のリスト」と「訪問後14日以内のリスト」で、どちらのCPAが低いかを比較する。
- 入札単価調整率のテスト:「訪問後3日以内のリスト」への入札単価を「+50%」にした場合と「+80%」にした場合で、ROASがどう変化するかを検証する。
- クリエイティブのテスト:「訪問後7日以内のリスト」に対して、「クーポン訴求のバナー」と「レビュー訴求のバナー」のどちらがクリック率やコンバージョン率が高いかをテストする。
重要なのは、一度のテストで検証する要素を一つに絞ることです。期間とクリエイティブを同時に変えてしまうと、どちらの要素が結果に影響したのか判断できなくなります。主要な広告プラットフォームにはA/Bテスト機能が標準で搭載されているため、これらを活用して厳密なテストを実施しましょう。
主要指標(CVR, CPA)の分析と改善サイクル
A/Bテストを実施したら、結果を正しく分析する必要があります。注目すべき主要な指標は、コンバージョン率(CVR)と顧客獲得単価(CPA)です。
- 仮説設定:「検討期間の短い商材なので、リーセンシーを7日から3日に短縮すれば、より意欲の高いユーザーに絞られCPAは改善するはずだ」といった仮説を立てます。
- テスト実施:仮説に基づき、Aパターン(7日間)とBパターン(3日間)の広告セットを用意し、同予算・同期間で配信します。
- 結果分析:配信結果を比較し、CPAやCVR、ROASといった指標でどちらのパターンが優れていたかを評価します。統計的な有意差があるかどうかも確認することが望ましいです。
- 改善と水平展開:テストで優れていたパターン(勝ちパターン)を本格導入します。そして、また新たな仮説を立てて次のテストを計画する。この「仮説→実行→検証→改善」のPDCAサイクルを回し続けることが、リーセンシー戦略を常に最適な状態に保つための唯一の方法です。
【最重要】Cookie規制とリーセンシーの未来:今すぐ始めるべき対策
これまで解説してきたリーセンシー戦略の多くは、ウェブサイトを横断してユーザーを追跡する「3rd Party Cookie(サードパーティクッキー)」という技術に依存してきました。しかし、プライバシー保護の世界的な潮流を受け、この3rd Party Cookieはまさに風前の灯火です。SafariやFirefoxではすでにブロックが強化されており、市場で最大のシェアを誇るGoogle Chromeでも段階的な廃止が進んでいます。これは、従来のリターゲティング広告の仕組みそのものが崩壊することを意味し、リーセンシー戦略の根幹を揺るがす、避けては通れない重大な課題です。
3rd Party Cookie廃止がリーセンシー戦略に与える致命的な影響
3rd Party Cookieが利用できなくなると、具体的に何が起こるのでしょうか。それは、「サイトを離脱したユーザーを、他のサイト上で正確に識別し、追いかけること」が極めて困難になるということです。つまり、これまで当たり前のように作成していた「サイト訪問後〇日以内のユーザー」というリターゲティングリストの精度が著しく低下、もしくは作成自体が不可能になります。結果として、リーセンシーに基づいたきめ細やかな入札調整やクリエイティブの出し分けといった戦略は、その効果を大きく損なうことになります。これはもはや遠い未来の話ではなく、今この瞬間にも対策を始めなければならない喫緊の経営課題です。
ポストCookie時代を乗り切るための3つの代替策
では、私たちは指をくわえて待つしかないのでしょうか。いいえ、打つ手はあります。ここでは、ポストCookie時代においても広告効果を維持・向上させるための、3つの重要な代替策をご紹介します。
代替策1:コンバージョンAPI(CAPI)とサーバーサイドGTMの導入
最も強力で確実な対策が、コンバージョンAPI(CAPI)の導入です。これは、ユーザーのブラウザ(クライアントサイド)を介さず、自社のサーバーから直接広告プラットフォーム(MetaやGoogleなど)のサーバーへ顧客の行動データを送信する仕組みです。
- 仕組み:ユーザーがサイトで商品を購入すると、その情報が自社サーバーに記録されます。そのサーバーからAPI連携でMeta社のサーバーに「〇〇さんが購入しました」というデータを直接送るため、ブラウザのCookie規制の影響を一切受けません。
- メリット:Cookieに依存しないため、より正確で信頼性の高いデータ計測が可能になります。iOS14のアップデート等で失われたコンバージョンデータを補完し、広告配信の機械学習の質を維持・向上させることができます。結果として、オーディエンスリストの精度が保たれ、リーセンシーに近い考え方でのターゲティングを継続することが可能になります。サーバーサイドGTM(Googleタグマネージャー)と組み合わせることで、より柔軟なデータ送信が実現できます。
代替策2:1st Party Data(自社データ)の徹底活用
Cookieが他社(3rd Party)のデータであるのに対し、自社で収集した顧客データは「1st Party Data」と呼ばれます。これはポストCookie時代の最も貴重な資産となります。
- 具体例:メールアドレス、電話番号、会員ID、実店舗での購買履歴など。
- 活用法:これらの顧客リストをハッシュ化(暗号化)して広告プラットフォームにアップロードすることで、「カスタムオーディエンス(Meta)」や「顧客リスト(Google)」として広告配信に活用できます。例えば、「過去30日以内に購入した顧客リスト」を除外したり、「休眠顧客リスト」に対して特別なオファーを配信したりと、Cookieに頼らない精緻なターゲティングが実現可能です。
代替策3:共通IDソリューション(Unified ID)の活用
これは、複数のメディアやプラットフォームを横断して利用できる、プライバシーに配慮した新しい形の共通IDを生成する技術です。
- 仕組み:ユーザーが同意の上で提供したメールアドレスなどを基に、暗号化されたIDを生成。ユーザーがそのIDに対応した別のサイトを訪れた際に、同一ユーザーとして認識し、ターゲティングを可能にします。
- メリット:3rd Party Cookieの代替として、ドメインを横断したユーザー追跡を可能にし、リターゲティング広告のリーチと精度を維持することが期待されています。導入には対応しているベンダーとの連携が必要ですが、今後の重要な選択肢の一つとなるでしょう。
これらの対策は、もはや「やってもいいこと」ではなく「やらなければ生き残れないこと」です。早期の検討と導入を強く推奨します。
効果は実証済み!リーセンシー活用による成功事例
最後に、リーセンシー戦略がいかに強力であるかを示す、具体的な成功事例をいくつかご紹介します。
事例1:アパレルECサイト|カート離脱者への即時アプローチでCVRが25%向上
あるアパレルECサイトでは、カートに商品を入れたものの購入に至らなかったユーザーに対し、リーセンシーを「1時間以内」「24時間以内」「3日以内」と細かく分割。特に離脱後1時間以内のユーザーには、入札を最大強化し「今なら使える500円OFFクーポン」付きのダイナミック広告を配信した結果、リターゲティングキャンペーン全体のコンバージョン率が25%も向上し、ROASが大幅に改善しました。
事例2:BtoB SaaS企業|段階的な情報提供で商談化率が30%改善
比較検討期間が長いBtoBのSaaSツールを提供する企業では、リーセンシーに応じて提供するコンテンツを変更。「訪問後7日以内」のユーザーにはサービスの概要動画を、「8日〜30日」のユーザーには詳細な導入事例のホワイトペーパーを、「31日〜60日」のユーザーには個別相談会の案内を配信。このようにユーザーの検討フェーズに寄り添った結果、単なる資料請求数だけでなく、最終的なゴールである商談化率が以前の施策と比較して30%も改善しました。
事例3:【Cookieレス対応】旅行代理店|コンバージョンAPI導入で予約率20%向上
iOSのアップデート以降、リターゲティング広告の成果が悪化していたある旅行代理店は、Meta社のコンバージョンAPIを導入。ブラウザ経由では欠損していたコンバージョンデータをサーバーサイドから直接送信することで、機械学習の精度が回復。最適化された広告配信が可能となり、特に「サイト訪問後3日以内のユーザー」への広告配信の精度が向上し、キャンペーン全体の予約率が20%向上、CPAも15%削減することに成功しました。
まとめ:リーセンシーの最適化は、もはや選択ではなく必須の時代へ
本記事では、運用型広告におけるリーセンシーの重要性から、具体的な戦略、そしてポストCookie時代を見据えた未来の対策までを包括的に解説いたしました。リーセンシーとは、単なる広告運用のテクニックではありません。それは、顧客一人ひとりの「今」の心理状態を深く洞察し、最適なコミュニケーションを図るための、マーケティングの根幹に関わる思想です。サイト訪問からの経過時間に応じて、アプローチの強弱を変え、メッセージを最適化し、そして見込みのないユーザーからは静かに去る。このメリハリの効いた戦略こそが、無駄な広告費を削り、CPAを改善し、ROASを最大化するための最も確実な道筋です。そして、3rd Party Cookieという航海図が失われつつある今、コンバージョンAPIや1st Party Dataといった新しい羅針盤を手にいれ、データに基づいたリーセンシー戦略を再構築できる企業だけが、これからのデジタル広告の荒波を乗り越えていくことができるでしょう。まずは、自社の広告アカウントのオーディエンスリストを見直すことから始めてみてください。そこに、貴社のビジネスを飛躍させる大きなヒントが眠っているはずです。
最終文字数:6998
当社では、AI超特化型・自立進化広告運用マシン「NovaSphere」を提供しています。もしこの記事を読んで
・理屈はわかったけど自社でやるとなると不安
・自社のアカウントや商品でオーダーメイドでやっておいてほしい
・記事に書いてない問題点が発生している
・記事を読んでもよくわからなかった
など思った方は、ぜひ下記のページをご覧ください。手っ取り早く解消しましょう
▼AI超特化型・自立進化広告運用マシンNovaSphere▼

![デジマラボ [Digima Labo] by NpvaSphere(旧チャンキョメ)](https://digima-labo.com/wp-content/uploads/2023/06/logo_dezimalabo_2212763.png)