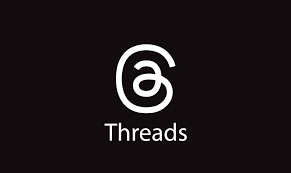宣伝失礼しました。本編に移ります。
発表の要点と背景
データ・ワンは二〇二五年九月二十九日、味の嗜好データを用いた新たな広告配信サービス「co-buy 味覚嗜好ターゲティング」を発表しました。伊藤忠商事および味香り戦略研究所と連携し、味覚センサーによって商品そのものの味を定量化し、二十二の嗜好タイプから該当消費者群を推定して配信までつなぐ仕組みです。実証にはサッポロビールの「サッポロ男梅サワー」を用い、嗜好性訴求のクリエイティブが通常配信より高い反応を得たこと、味が近い商品どうしの同時購買傾向が確認されたことが示されました。同社は国内最大級の四千五百万ID規模の購買データ基盤を背景に、購買検証まで一気通貫で支援していく方針です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発表日 | 二〇二五年九月二十九日 |
| 連携先 | 伊藤忠商事、味香り戦略研究所 |
| 技術要素 | 味覚センサー、二十二嗜好タイプ、フードペアリング解析 |
| 検証商品 | サッポロ男梅サワー |
| 基盤データ | 小売横断IDPOS、四千五百万ID規模 |
| 示唆 | 嗜好性訴求が高反応、近接味商品の同時購買傾向 |
なぜ今、味覚から始めるのか
従来のデジタル広告は、行動履歴や属性情報に依拠しながらも、実際の購買へとつながる欲求の核に触れきれていませんでした。人が商品を選ぶ最後の一押しは、価格でもブランドでもなく、しばしば「おいしさ」という極めて主観的な体験です。おいしさは感情のトリガーであり、生活のリズムに溶け込む反射的な選択を導きます。味覚は記憶と結びつきやすく、身体感覚として反復学習されるため、一度はまると習慣化しやすい特性があります。したがって、味覚の好みを精緻に把握し、購買実績と照合して広告を提示できれば、興味喚起から購入意思決定までの距離を一気に縮めることができます。さらに、味覚はカテゴリー横断の連想を生みやすく、飲料から菓子、惣菜から調味料へと自然に橋渡しされるため、ひとつの嗜好から複数の売場を活性化できます。
消費者の認知負荷が高まるなかで、バナーや動画の訴求は秒単位で取捨選択されます。情報量が限られた接触の瞬間に、記号的なベネフィットや抽象的な世界観だけでは行動の変化を引き起こしにくいのが現実です。味覚は、瞬時に身体の記憶を喚起させる引き金として機能し、写真がなくとも言葉や数値から質感を想起させることができます。これは、単に食領域だけでなく、香りや触感に寄り添うカテゴリーにも汎用化できる思考法です。さらに、プライバシー規制の強化が進む現在、ウォールドガーデンの指標だけに依存した最適化は陳腐化しつつあります。味覚という一次データに近い感性情報と実購買の一次データを組み合わせる設計は、サードパーティCookie後の世界でも持続的に機能します。データの耐用年数という観点でも、味覚は短命なトレンド指標に比べて半減期が長く、学習の再利用効率が高いのです。
抽出→診断→抽選→配信→検証 味覚→嗜好→購買→広告→差分 数値→タイプ→商品→接触→学習
「co-buy 味覚嗜好ターゲティング」の中枢
本サービスは、対象商品の味わいを定量化し、その味を好む可能性が高い消費者群を推定して広告を配信する仕組みです。味覚センサーによって抽出された味のプロファイルを出発点に、嗜好性アルゴリズムが二十二の嗜好タイプへと分類し、どの群に響くかを診断します。さらに、フードペアリング解析を重ねることで、味の近接性から「よく一緒に買われる」周辺商品を見つけ出し、購買者セグメント単位でメディア配信までつなぎます。購買データ、モバイルID、店舗横断IDの統合により、配信から検証までが一気通貫で回る点が特長です。検証段階では広告接触者と非接触者の実購買行動の差分を捉え、次の配信に学習を反映します。
この仕組みは、発見から検証までの距離を最短に設計しています。まず、味のプロファイルに合致する潜在層を推定し、彼らが普段から購入している商品の購買者セグメントへ広告を投下します。これにより、メディアプランニングは「その人が今いる売場」に直接アクセスする発想へと転換されます。従来の興味関心ターゲティングでは辿り着けなかった「未認知だが好みに合う」層を拾い上げ、新しい買い物の導線を生み出します。運用の現場では、嗜好タイプごとにメッセージとレイアウトの骨子をテンプレート化し、味の特徴が異なる複数のクリエイティブを同時に走らせます。広告ログと購買ログを突合することで、どの表現がどの嗜好タイプに効いたのかを解像度高く把握でき、次の制作と配信のループが高速化します。
| 甘味 | ■■■■■ |
| 酸味 | ■■■■ |
| 塩味 | ■■■■■■ |
| 苦味 | ■■ |
| 旨味 | ■■■■■ |
| 渋味 | ■■ |
味を測るという革新
味を数値化する技術は、単なる官能評価の置き換えではありません。人の舌の受容を模したセンサーは、甘味、塩味、酸味、苦味、旨味、渋味といった基本味を電気信号として捉え、後味やボディ感といった飲食体験の厚みまで表現します。これにより、レシピや成分表示だけでは予測しづらい「感じ方」をデータとして扱えるようになります。長年蓄積された味覚データベースと組み合わせることで、似た味わいのクラスタリングや、嗜好タイプの推定精度が高まります。味の距離が購買の距離に相関するという発想は、レコメンドの世界に新しい座標軸を持ち込みます。
味覚センサーが示す数値は、研究機関の実験室だけのものではありません。現場に運用可能なスピードと再現性が確保されており、ラインアップや配合の微調整と広告設計を同じダッシュボードで議論することができます。定量データは、議論を感覚的な好みから開放し、開発、販促、広告、店舗運営の関係者が同じ一点を見つめるための共通言語として機能します。また、嗜好性診断は集団の平均像だけでなく、個人差の豊かさを描き出します。二十二の嗜好タイプは、似た味でも異なる理由で好まれる微妙な違いを識別します。甘味の支持が同じでも、酸味とのバランスを重視する群と香りの立ち上がりを重視する群では、訴求すべき語彙がまったく変わります。
| 軸 | 軽快 | 濃厚 |
|---|---|---|
| 爽快 | 酸味強 | 香り立 |
| 深味 | 余韻短 | 余韻長 |
実証が示した連想の連鎖
実証では、あるレモンと塩の輪郭が際立つリキュール系飲料の味わいを定量化し、その特徴が強く現れる嗜好タイプに向けて訴求しました。すると、直接的な同カテゴリー内の反応に加え、日常的に濃いめのコーヒーや塩味の効いた即席麺、濃厚なスナック菓子の購買者からの反応が顕在化しました。味覚の近接性が、カテゴリを越えた「いつもの買い物」の中に潜む連想を刺激し、ついで買いの確率を押し上げたのです。嗜好性を言語化したコピーに替えるだけで、同じ広告枠でも体感的な説得力が大きく変わり、クリックから棚前の選択までの移行が滑らかになりました。
実証で観測された反応は、キャンペーン施策の枠を超えた学びをもたらしました。味の輪郭が近い商品は、売場が違っても生活者の頭の中では同じ棚に並びます。塩味のキレと余韻の心地よさを訴求したコピーは、甘味と酸味のバランスを重視する嗜好タイプにも副次的な興味を生み、週末のまとめ買いのリストに新顔を滑り込ませました。広告は、思い込みを上書きするのではなく、すでにある好みの延長線上に新しい選択肢をそっと差し込む役割を果たしました。この結果は、クリエイティブの言葉選びだけでなく、配荷の優先順位にも示唆を与えます。嗜好タイプごとの偏在が強いエリアでは、関連商品の同時露出を高めることで、広告を見た後の買い回りが加速します。味の地図を読み解くことは、物流と在庫の地図を同時に描くことに等しいのです。
味測定→嗜好推定→連想抽出→配信→購買検証→学習 一週間→二週間→一週間→一週間→一週間→継続
従来手法との決定的な違い
興味関心ベースのターゲティングは、検索や閲覧といった明示的シグナルに引きずられやすく、一時的な話題性に左右されます。一方、味覚は日常の反復で形づくられた情動の習慣であり、時流に対して鈍感なぶん、購買行動の安定的な予測因子になり得ます。広告の設計に嗜好性を持ち込むことで、短期のクリックに偏らない継続的な反応が得られる可能性が高まり、季節や気分のノイズに埋もれない設計が可能になります。加えて、味覚は家族内伝播や地域文化との連動性が高く、配荷や棚割りの意思決定にも示唆をもたらします。
嗜好性を使った配信がもたらす効果は、クリック率や購買率といった定量指標の改善に留まりません。広告の物語が、生活者の物語と共振しやすくなるのです。人は、抽象的な効用よりも、身体が理解する比喩に強く反応します。「苦味が抑えられて深い余韻が続く」という一文は、味覚を持つ読者の想像力に直接届きます。そこに、いつもの買い物リズムへ滑り込む導線を添えれば、無理のない新習慣が生まれます。さらに、嗜好性は価格訴求の負のスパイラルを回避します。割引やポイントだけに頼る促進は、短期的な反応を引き出しても、価値の記憶に残りにくい傾向があります。味の記憶を更新するコミュニケーションは、価格に左右されにくい選好の芯を育て、次の指名買いの理由を積み上げます。
| 興味関心 | 一過性に強い | 嗜好習慣の把握は弱い |
| 味覚嗜好 | 習慣に強い | 季節変動に頑健 |
データ統合が拓く到達と検証
小売横断の実購買データとモバイルIDがつながることで、広告の到達は単なるインプレッションから「買ったかどうか」という確かな指標へと回帰します。購入実績から逆算した見込み客抽出、嗜好タイプに沿ったクリエイティブ生成、セグメント別の配信、実購買検証という一連のプロセスが、ひとつのデータの幹に束ねられます。これにより、メディアの評価がクリック至上主義から脱し、売場との対話を取り戻します。実店舗とオンラインの境界は薄れ、広告が販促と地続きになるのです。
一気通貫の設計は、広告の最適化を属人的な経験則から解放します。同じダッシュボード上で、味覚由来のセグメント、配信メディア、クリエイティブ、実購買の差分がひと目で比較できます。これにより、PDCAの一周が短縮され、仮説の粒度が揃います。現場は感覚的な反省会から、因果を検証する振り返りへと進化します。また、購買を基点にした評価は、媒体横断での比較を容易にします。指標が統一されることで、チャネルの役割分担が明確になり、無駄な重複接触が減少します。広告は、生活者が動くタイミングを見計らって現れ、消えるべき時に潔く消えるようになります。
購買ID→広告ID→配信→購買差分→最適化 基盤統合→可視化→比較→学習→還元
クリエイティブはどう変わるか
嗜好性訴求クリエイティブの要は、味覚の輪郭を直感的に想像させる言語と構図です。甘味や酸味の強さ、香りの立ち上がり、余韻の長さといった体感語彙でコピーを編み、写真がなくとも脳内で味が立ち上がる説明を添えます。例えば「塩のキレが余韻を締める」「苦味を抑えた深いコク」という言葉は、味覚センサーの数値と一致するため、誇張に頼らない説得が可能です。レビューの断片をただ羅列するのではなく、嗜好タイプごとに刺さる比喩を準備すると、同一商品でも異なる角度で訴求できます。
味覚データがあることで、表現の冒険が可能になります。例えば、同一商品の広告でも、爽快な酸味を求める嗜好タイプには輪郭のシャープさを強調し、コクを求めるタイプにはボディ感と余韻を押し出すコピーに差し替えます。画像がなくても、言葉と配置だけで味の像を立ち上げることができます。見出し、本文、補足の三層で訴求を設計し、余韻に商品の連想を忍ばせると、クリック後の行動が自然に続きます。さらに、レビューやSNSの文脈を借りるのではなく、味覚センサーの数値に裏打ちされたコピーを用いることで、誇張や過度な主観に頼らない説得が成立します。伝えるべきは事実の魅力であり、過剰な装飾ではありません。
| 嗜好タイプ | 見出し例 | 本文例 |
|---|---|---|
| 爽快志向 | 塩のキレと酸の伸び | 輪郭のシャープさが後味を軽く保ちます |
| コク志向 | 苦味を抑えた深い余韻 | 厚みのあるボディ感が満足感を引き上げます |
類似ソリューションとの違いを読む
レシピ閲覧やアンケートを基盤にした食嗜好DMPは、意図の明示性という強みを持ちます。一方で、実際の味わいと嗜好タイプを結ぶ教師データが薄いと、類似レシピの閲覧や一過性の関心に引っ張られ、購買への連結が弱くなる懸念があります。味覚センサー由来の定量データと購買IDを起点にするアプローチは、味と買い物のあいだの距離を直接に詰めます。さらに、フードペアリング解析で味の組み合わせを科学的に紐づけることで、クロスカテゴリーの拡張設計が容易になります。つまり、興味の推定から「味の実体」へと推論の始点を置き換える点に、決定的な差が存在します。
食嗜好領域では、博報堂DYメディアパートナーズと楽天が展開する食特化DMP「TastechEngine」のように、レシピ閲覧やアンケートデータから食の傾向を推計する枠組みが先行してきました。これらは食生活の変化を素早く捉える点で有効です。対して、味覚センサー起点のアプローチは、商品そのものの味という実体から嗜好を推定し、購買ログに直結させる点に重心があります。両者は補完関係にあり、上流の意図と下流の体験を往復しながら学習を深めることが理想です。
| 起点 | 上流(意図) | 下流(体験) |
|---|---|---|
| レシピDMP | 閲覧・意欲 | 購買への距離が残る |
| 味覚センサー | 味の定量 | 購買に直結 |
活用シーンの拡張
新商品の立ち上げ時に、味の輪郭を核にしたセグメントを先行抽出し、認知前から想定ファン層へ染み込ませる。季節商材では、気温や食卓の変化に伴う味覚の求心性を支えるように、酸味やスパイスの効いた商品の訴求比率を滑らかに変化させる。定番商品のテコ入れでは、飽きの相殺として味の親和性が高い周辺商品の組み合わせを提示し、食卓の文脈ごと刷新する。外食や中食の分野では、メニューの味プロファイルを可視化し、来店前の期待値と提供体験のギャップを埋める。いずれも、味覚を媒体化するという発想が鍵になります。
リアルタイムの状況変化にも、味覚は柔軟に対応できます。気温や湿度、時間帯が変われば欲する味も変わります。午後の眠気には苦味の軽い酸味、夜のリラックスには塩味を抑えた旨味など、日内リズムごとの訴求を想定して配信を切り替えると、生活者の体感に寄り添った接触が実現します。利便性を訴えるよりも、心地よさを作るほうが、習慣は長続きします。また、外食や中食の文脈では、メニュー間のフードペアリング提案が新しい客単価の伸びを生みます。味の親和性に基づく組み合わせは、単なるおすすめではなく、体験の質を底上げする構成提案になります。
| 春 | 爽快な酸味を強化 |
| 夏 | 清涼感と塩のキレ |
| 秋 | 旨味と香りの厚み |
| 冬 | 余韻の長さとコク |
ブランドと小売の共鳴
メーカーと小売が味覚という共通言語を持てば、売場の意思決定は「売れているから置く」という受動的判断から、「この味の潮流を育てる」という能動的選択へと転じます。小売横断の購買データは、地域や時間帯ごとの味の偏りを可視化します。これを基に陳列やキャンペーンの設計を調整すれば、広告の電波が店舗オペレーションへと伝導し、棚前体験が統合的に最適化されます。ブランドは商品の核である味を語り、小売は地域に根ざす味の文脈を編み、双方の物語が一致した瞬間に、指名買いとついで買いの両輪が回り始めます。
共通言語が手に入ると、対話は速くなります。ブランドは開発の裏付けとして味覚センサーの数値を提示し、小売は地域の嗜好分布と照らして露出設計を決めます。双方が「どの味に、どの言葉で、どの場面で」臨むのかを合意できれば、販促と広告が別々に走る非効率は消えていきます。味の潮流を育てる視点が定着すれば、新カテゴリの創造も視野に入ります。さらに、共同検証を通じて得られた知見を共有すれば、競争は消耗ではなく学習に変わります。地域の祭事や学校行事など、生活のイベントと味の求心性を重ねた設計は、地域に根ざした売場づくりの王道です。
開発→味覚数値→言語化→配荷→露出→検証→共有 メーカー⇄小売の往復で潮流を育てる
実装における留意点
同意と透明性の設計は、味覚データ活用において最優先です。購買データとIDをまたぐ連携は、目的の限定、利用範囲の明確化、ユーザーにとっての価値の提示を三位一体で満たす必要があります。また、味覚は文化的背景や健康状態など複数の要因に揺れます。短期の反応に過剰最適化せず、季節性やライフステージの変化を織り込んだテスト計画を継続することが重要です。加えて、嗜好タイプのラベリングは説明可能性を備えるべきであり、マーケティングの現場が理解し、語れる言葉で設計することが実装速度を左右します。
説明責任は、信頼の前提です。嗜好タイプの意味、データの収集方法、利用の目的と期間、第三者提供の有無を明確にし、生活者が選択できる仕組みを整えます。オプトアウトや同意の更新を煩わしいものにしない配慮が、長期的な関係を支えます。味覚は個人の経験に深く関わる情報であるからこそ、扱いは丁寧でなければなりません。また、季節や体調で嗜好が揺れる現実を前提に、継続的なテスト設計を用意します。短期の反応を誇張せず、複数の期間で効果の再現性を確かめ、運用に反映します。多様性を認める姿勢が、過学習を防ぎ、拡張可能な仕組みを育てます。
| 目的限定 | 収集・利用の範囲明確化 |
| 説明可能 | 誰にでも語れるラベリング |
| 選択権 | 容易な同意更新と撤回 |
これからの「おいしさ」の売り方
味の科学と購買の現実が握手したことで、広告はより身体的なコミュニケーションへと進化します。味覚の地図を読むことは、生活者の一日を読み解くことと同義です。朝の覚醒から夜の安らぎまで、どの場面でどの味が求められるのかを理解し、そこにふさわしい商品と体験を重ねていく。広告が押しつけではなく、日々のリズムに沿う提案に変わったとき、ブランドと生活者の距離は最短になります。味覚から始めるマーケティングは、派手な演出を過剰に求めません。静かな合点が、確かな売上を連れてきます。
広告が果たすべき役割は、選ぶ理由を押し付けることではありません。生活者がすでに持っている好みの軸に、静かに光を当てることです。味覚から始まるコミュニケーションは、身体の記憶に優しく刻まれ、やがて無意識の選択を更新していきます。派手な演出や過剰な割引よりも、しっかりとした体験の輪郭を提示することが、長い信頼を築きます。味覚を介した設計は、家庭の食卓、職場の休憩室、移動中の小さな買い物など、日常の隅々にまで届きます。広告が生活の風景に溶け込み、売場が広告の続きを受け止める。その往復運動こそが、新しい当たり前になります。
朝→軽やかな酸味 昼→香りの立ち上がり 夜→余韻の深さ 体験の地図にあわせて提案が寄り添う
社内実装を加速させる運用設計
部門横断のプロジェクトにおいては、意思決定の速度と一貫性が成果を左右します。味覚データを中核に据える運用では、商品企画、研究開発、営業、販促、広告運用、データ基盤の各チームが同じ仮説に立つことが重要です。まず、対象商品の味プロファイルを共有し、嗜好タイプごとに「刺さる理由」を具体的な語彙で定義します。続いて、購買実績から逆算したセグメントの想定規模と接触可能メディアを整理し、制作と配信のカレンダーを固定します。最後に、購買検証の読み解き方を事前に決め、次回配信への反映ルールを明文化します。手順の事前合意が、現場の迷いを取り除き、走りながら学べる余白を生みます。
現場の心理的安全性も無視できません。新しい指標やアルゴリズムへの不安を減らすには、可視化の設計が効きます。味覚プロファイルとクリエイティブ、配信、購買の相関が一望できるビューを用意し、仮説と結果の対応を誰もが言葉にできる状態を保ちます。納得感のある説明可能性は、現場の主体性を引き出します。
| 設計 | 仮説の共有と言語化 |
| 運用 | 日程固定と役割分担 |
| 学習 | 読み解きルールの明文化 |
法的整理と倫理の実務
味覚に関する情報は感性に関わるデータであり、たとえ個人情報の定義に直結しない場合でも、取り扱いには慎重さが求められます。利用目的の特定、第三者提供の有無、保存期間、同意撤回の手段を明確にし、わかりやすい言葉で提示します。社内では、目的外利用の防止とアクセス権限の最小化を徹底し、監査のログを残す運用を標準にします。さらに、嗜好タイプの推定が本人の不利益につながらないよう、差別や偏見を助長しないコミュニケーションの原則を定めます。
透明性の確保は、長期的なブランド価値の土台です。生活者にとっての価値を常に対価として提示し、選択権を尊重する姿勢を崩さない限り、味覚をめぐるマーケティングは豊かな文化を育てます。
透明性→選択権→最小収集→限定利用→監査可能→信頼
三年後の風景
味覚データの社会実装が進むと、広告は一層コンテクストに馴染みます。店舗では、エリアの嗜好分布に応じて陳列が滑らかに変わり、季節や天候で味の提案が更新されます。メニューは味の地図に直結し、買い物は自分の好みの再発見へと変わります。ブランドは、単なる商品提供者ではなく、味の編集者としての役割を担います。生活者は、自分の好みを言語化する楽しみを手に入れ、家族や仲間と共有しながら、豊かな食卓を日々つくっていきます。
広告の役割は、派手に叫ぶことから、静かに伴走することへ。味覚をめぐる物語が積み上がるほど、社会は穏やかに豊かになります。
| 店舗 | 嗜好分布に応じた陳列の自動調整 |
| 広告 | 体験起点の静かな伴走 |
| 生活 | 好みの言語化と共有 |
当社では、AI超特化型・自立進化広告運用マシン「NovaSphere」を提供しています。もしこの記事を読んで
・理屈はわかったけど自社でやるとなると不安
・自社のアカウントや商品でオーダーメイドでやっておいてほしい
・記事に書いてない問題点が発生している
・記事を読んでもよくわからなかった
など思った方は、ぜひ下記のページをご覧ください。手っ取り早く解消しましょう
▼AI超特化型・自立進化広告運用マシンNovaSphere▼

![デジマラボ [Digima Labo] by NpvaSphere(旧チャンキョメ)](https://digima-labo.com/wp-content/uploads/2023/06/logo_dezimalabo_2212763.png)