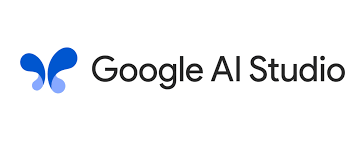ぶっちゃけ「知識」が必要なのではなく、今すぐ結果が欲しい!という方へ
宣伝失礼しました。本編に移ります。
生活者の購買行動が、いよいよ決定的な転換点に到達いたしました。ECと実店舗を状況に応じて使い分ける「ハイブリッド消費者」が日本で多数派になったという最新調査結果です。しかも、体験の主戦場は「どちらで買うか」ではなく「どちらも自然につながるか」へと移りました。本稿では、博報堂の最新調査を軸に、経済産業省の市場データ、業界横断の検証結果を重ね合わせながら、ニュース性の高いインサイトを徹底解説いたします。結論は明快です。「ハイブリッド」はもはや選択肢ではなく前提であり、勝敗は“同期(シンク)”の速さで決まります。

速報:生活者の“二刀流”がついに多数派(52.3%)。購買金額の主役でもある
博報堂の調査では、20〜69歳の生活者のうち、ECと実店舗を日常的に併用する「ハイブリッド消費者」が過半を占め、ECにおける日用品の購入金額でも圧倒的な存在感を示しました。これは、単なるチャネル選好の話ではございません。購買の意思決定と受け取り体験の設計を、両チャネルの横断前提で再構築すべき段階に入ったことを意味します。【ハイブリッド消費の概況(博報堂×買物研究所)】 ハイブリッド消費者比率 ┃███████████████████████████████ 52.3% 非ハイブリッド層 ┃███████████████████████████ 47.7% EC日用品購入金額に占める比率 ┃████████████████████████████████████████████████████ 81.8% (ハイブリッド層の寄与)すなわち「売上の山」は併用層の真ん中にあります。広告・販促・在庫・受け取り導線の意思決定を、EC専属・店舗専属で分断したままでは取り逃がしが生じるのは必然でございます。
不満の震源地は“つながらないこと”──半数(50.2%)が横断体験に不満
多数派となったハイブリッド消費者の半数が、オンラインとオフラインをまたぐ過程に不満を抱えています。最も多いのは「欠品商品の入荷情報がわからない」、次いで「ECと店舗のポイント非連携」、「ECと店舗で価格が異なる」。いずれも「情報の同期」が遅い/できていないことが根っこにあります。【横断体験の不満(上位)】 1 欠品入荷情報が不明 ┃████████████████████████████ 54.4% 2 ポイントがEC/店舗で非連携 ┃███████████████████████████ 52.5% 3 ECと店舗の価格差がある ┃██████████████████████████ 50.6% (「不満」「やや不満」の合計率)「情報の同期」はUXの装飾ではなく、売上と信頼の根幹です。棚の在庫、価格、ポイント、クーポン、入荷通知、購入履歴、返品可否……これらがチャネル横断で同時に“同じ事実”を示せるかどうかが、購買決定の分水嶺でございます。
生活者が「今、実装してほしい」体験──受け取りの自由・入荷通知・ポイント連携
望まれているのは派手な新機能ではありません。確実に使う・役に立つ“摩擦の除去”です。受け取り方法の選択(配送/店舗受取/ロッカー等)、欠品時の即時入荷通知、ポイントの一本化が上位に並びます。まずはここから通すだけで、体験のズレは劇的に減少いたします。【魅力度が高い体験(上位)】 受取方法を自由に選べる(配送/店舗受取) ┃██████████████████████ 69.7% 欠品商品の入荷を即時通知 ┃█████████████████████ 67.4% ECと店舗のポイント連携 ┃█████████████████████ 67.3% 価格・プロモーションの統一 ┃████████████████████ 67.1% 店頭返品の即時返金 ┃███████████████████ 65.3%この“トップ3”は、いずれもシステム連携と運用定義の整備で現実的に実装可能です。最短距離で効く「生活者の期待のど真ん中」と言えます。
市場の現在地:BtoC-ECは26.1兆円(前年比+5.1%)、EC化率は9.8%。カテゴリー別の温度差も明確
国内のEC市場は堅調に拡大していますが、カテゴリごとにEC化率の“温度差”がはっきり出ています。特にメディア・家電は高水準、家具・生活雑貨も伸長。一方で生鮮・食品は心理的ハードルや物流の制約で伸び代を残しています。施策優先順位は、この温度差を踏まえて設計すべきです。【物販のEC化率(2024年、日本)】 書籍・映像・音楽ソフト 56.45% │███████████████████████████████ 生活家電・AV機器・PC等 43.03% │█████████████████████████ 生活雑貨・家具・インテリア 32.58% │███████████████████ (BtoC-EC全体のEC化率は 9.8%) 市場規模合計(BtoC-EC 3分野) 26.1兆円(前年比 +5.1%)数字が示すのは「一律の打ち手は通用しない」という事実です。カテゴリの物性・購入頻度・返品コストに応じて、求められる“同期すべき情報”と“こぼしてよい摩擦”の設計は変わります。
ジャーニーの定番はROPOとウェブルーミング──情報探索と購入の順序は自在に入れ替わる
生活者は「ネットで調べて店舗で買う(ROPO/ウェブルーミング)」「店舗で確認してECで買う(ショールーミング)」の両方を併用します。検索・比較・動画レビュー・価格通知・在庫確認・ポイント還元──意思決定を支える情報はチャネルごとに役割が異なります。重要なのは、どちらの順序でも“同じ結論に着地できる”情報の一貫性です。【典型ジャーニー(例)】
[検索]→[レビュー/比較]→[店舗で体感]→[ECで最終購入]→[店舗受取/配送]
└───────────────[店舗で最終購入](在庫・価格・ポイントが一致)
情報の矛盾が発生した瞬間、生活者は“より信頼できる方”へ離脱します。信頼の源泉はスピードよりも「整合性」でございます。
店舗受取(BOPIS)は“もう特殊ではない”。浸透が示すメリットは送料ゼロと時間の自由
ECで購入し、店舗やロッカーで受け取る「BOPIS(Buy Online, Pick-up In Store)」は、配送混雑や即時性ニーズの高まりを受けて実装が加速しています。利用者ベースでは高頻度利用が相応に見られ、未利用者にも堅調な利用意向が確認されています。導入側のメリットは、配送費の抑制・店頭回遊の増加・返品の容易化。生活者にとっては「送料がかからない」「自分の時間で受け取れる」ことが最大の価値です。【BOPISの現況(国内調査の記載より)】 利用者のうち「月1回以上」利用 35% 未利用者の「今後使いたい」意向 36% (背景)送料回避・即時性・返品容易が主因まずは在庫連携と受け取りロジックの定義を明確化し、店舗オペレーション側の“負担感”を徹底的に減らす設計から着手するのが現実的です。
属性で違う“つまずきポイント”──不満は女性40代・60代に集中。個別最適の余地が大きい
横断体験への不満は、性・年代で濃淡が出ます。全体で50.2%が不満を感じる一方、女性40代・60代では比率が顕著に高いのが特徴です。家族内の購買意思決定や生活時間の制約、店頭接客への期待値など、行動文脈の違いが響いていると考えられます。ペルソナ別に、在庫通知の粒度・受取導線・返品可否・支払い手段を再設計すべきです。【性・年代別:横断体験への不満(抜粋)】 女性60代 ┃████████████████████████████ 63.0% 女性40代 ┃██████████████████████████ 59.1% 男性30代 ┃████████████████████ 51.2% 全体 ┃████████████████████ 50.2%セグメントの違いはコミュニケーション表現にも直結します。例えば「家族の予定で受け取り時間が読めない」層には、ロッカー受取や来店前決済の強調が効きます。
アパレル・食品・家電で異なる“触る/比べる/待てない”心理──設計は三者三様
アパレルは試着・触感を要するため、購入前に店舗で実物確認を求める傾向が強いカテゴリです。一方、家電は仕様比較の比重が高く、店舗での最終確認後にECで購入するケースも一定数存在します。食品は鮮度・賞味期限の安心感がハードルになりやすく、欠品時の代替提案と受け取り自由度の設計が欠かせません。【カテゴリ別の“決め手”イメージ】 アパレル:実物確認→サイズ/色の不一致を回避→(EC/店舗)で購入 家 電 :仕様比較→店頭で最終体感→(EC/店舗)で購入 食 品 :鮮度/期限の安心→受取自由→リピート継続ここで重要なのは、どの順路でも「在庫・価格・ポイント・返品規定」が一致していることです。体験の一貫性が、そのまま購買の一貫性になります。
グローバルの学び:オムニチャネル多数派(73%)は“より多く・より頻繁に”買う
海外の大規模研究では、複数チャネルを横断する買い手は、単一チャネルの買い手より購入額も来店頻度も高いことが確認されています。日本でも同じ傾向が進行中であり、「チャネル統合への投資」は売上の質(LTV・継続率)を底上げする最も堅実な道筋です。【示唆】 単一チャネル顧客<複数チャネル顧客(購入額/来店頻度) └ 複数チャネル体験の“同期”が価値の源泉「同期コスト」は「獲得コスト」を下げます。認知→比較→購入→受取→再購入のループが短く、太くなるためです。
実務でまず塞ぐ“体験の穴”──データ統合・価格/ポイント整合・入荷と在庫の可視化
何から着手するか。答えはシンプルです。第一に、購入履歴・在庫・価格・ポイント・クーポン・配送/受取のルールを一枚で定義し、全チャネルで同時に参照できる状態にします。第二に、店頭・EC・アプリの価格とプロモーションの整合を保つ運用の“締め”を決めます。第三に、入荷・欠品・取り置きの状態を顧客通知とスタッフ画面の双方で即時同期します。ここまでを通すだけで、上位不満の大半は鎮静化いたします。【最短で効く3点】 1 データの“単一の真実”を用意(在庫・価格・ポイント・受取) 2 価格/プロモーションの整合運用(例:更新責任とSLAを明確化) 3 欠品/入荷/取り置きの即時通知(顧客・スタッフ双方)やるべきことは技術よりも“定義”です。定義が固まれば、手段は複数ございます。
コピーライティングで“同期”を伝える──今日から使える訴求テンプレート
体験の価値を最短で伝えるのはコピーです。事実とベネフィットを一行で結合し、“手間の削減”を具体語で表現いたします。以下のテンプレートは、LP・店頭サイン・プッシュ通知・会員メールで横断的にお使いいただけます。【テンプレート例】 「アプリの価格、そのまま店頭で。」(価格整合) 「在庫、いま棚のどこにあるか見えます。」(在庫可視化) 「今日ECで買って、帰り道に受け取る。」(BOPIS) 「欠品は待たない。入荷した瞬間に通知。」(入荷即時) 「貯めたポイント、どこで買っても同じ価値。」(ポイント統合)重要なのは“安心の見える化”です。コピーの目的は機能紹介ではなく、迷いの除去にございます。
モール経済圏の現実──利用者数の拮抗と新興勢力の台頭は、同期設計の優先度をさらに引き上げる
国内の主要モールは利用者数が拮抗し、新興モールの急伸も続いています。生活者は複数モールを横断し、比較の起点はモール内検索・価格通知・レビューへ拡散。結果として、自社EC/実店舗の情報が片側だけ更新された瞬間に、比較の土俵から弾かれます。勝ち筋は「どこから来ても同じ結論に着地する情報設計」です。【インパクト】 モール横断の比較が常態化 → 自社の価格/在庫/ポイントの“遅延”が即座に露呈 → 「同期の遅延」=「信用の毀損」チャネルの重心が分散するほど、「同期の速さ」は効率の源泉になります。
ユニファイドコマースは“OMOの先”──顧客データと業務を一枚に束ね、現場で使える粒度に落とす
オムニチャネルが“つながる売り場”だとすれば、ユニファイドコマースは“つながる仕事”です。顧客プロファイル、在庫、価格、購入履歴、接客ログ、配送/受取のオペレーションを一つの基盤に束ね、スタッフの提示情報と顧客の体験をリアルタイムに同期させます。目指すべきは「顧客とスタッフが、同じ画面の同じ事実を見て話せる」状態です。【ユニファイドの到達点(例)】 ・店頭スタッフが顧客のEC閲覧/購入履歴を参照して提案 ・ECのカゴ内容が店頭来店で呼び出せる(棚位置ナビ付) ・消耗品の“補充タイミング”を推定し先回り通知ここに到達すれば、価格競争から体験競争へ軸足を移せます。差は「気持ちよさの秒単位」で生まれます。
ニュースの本質:価格格差より“情報の一貫性”。2025年の勝敗は「同期」でもう付いている
今回の最新調査が示すメッセージは極めてシンプルです。生活者の多数派が二刀流になったいま、勝敗を分けるのは「情報の一貫性」と「受け取りの自由」です。価格の一時的な差よりも、在庫・入荷・ポイント・返品・接客メモの“同時同期”が信頼をつくります。まずは「受取方法の選択」「入荷通知」「ポイント統合」の三点から着手し、次に価格・プロモーションの整合を固める。ここまで通せば、横断体験の不満の大半は解消し、売上の山の中心で戦えるようになります。総括:『買う前も、買った後も、ずっと同じ店』を設計する
ハイブリッド消費は目的地ではなく、出発点に過ぎません。生活者は、動画で学び、SNSで共感し、ECで買い、店で受け取り、アプリで返品します。どこで触れても「同じ店」と感じられる、一貫性のある買い物の記憶を設計できる企業だけが、2025年以降の標準となります。シンプルに申します。同期せよ。すべてを、同時に。生活者はもう準備ができています。
当社では、AI超特化型・自立進化広告運用マシン「NovaSphere」を提供しています。もしこの記事を読んで
・理屈はわかったけど自社でやるとなると不安
・自社のアカウントや商品でオーダーメイドでやっておいてほしい
・記事に書いてない問題点が発生している
・記事を読んでもよくわからなかった
など思った方は、ぜひ下記のページをご覧ください。手っ取り早く解消しましょう
▼AI超特化型・自立進化広告運用マシンNovaSphere▼

![デジマラボ [Digima Labo] by NpvaSphere(旧チャンキョメ)](https://digima-labo.com/wp-content/uploads/2023/06/logo_dezimalabo_2212763.png)