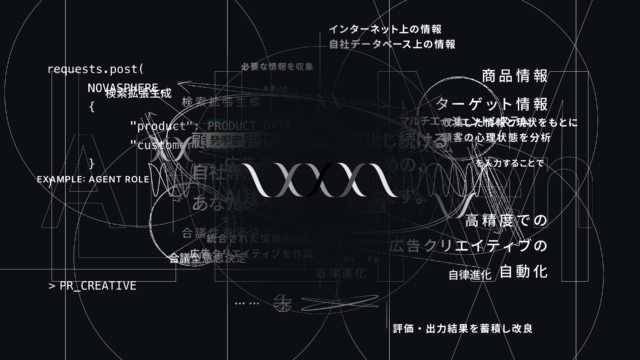宣伝失礼しました。本編に移ります。
販促の地殻変動が静かに始まりました。delyが始動した「クラシルリテールネットワーク」は、ばらばらに散っていた販促投資を一本の幹に束ね、生活者の手に還流させる仕組みです。複数の消費者向けアプリにまたがって同一の販促キャンペーンを横断配信し、実店舗での購買を条件に還元する購買保証型のモデルを採用しています。すなわち、出稿主が負担する販促費が、確かな購買という結果と引き換えに生活者へポイントとして戻る構造であり、媒体側も販促収益を新たに得られる三方良しのネットワークです。分断を前提に設計されてきた従来の販促は、ここで設計思想そのものの更新を迫られます。
この発表は単なる新サービスの開始ではありません。十数年にわたり広告と販促が別々に運用されてきた前提をリセットし、レシピ閲覧、特売確認、来店、購入、投稿という連続する行動をデータで束ね直す試みです。とりわけ注目すべきは「横断」と「購買保証」という二つのキーワードです。横断は、複数のアプリ横にまたがる面展開で認知と関心の取りこぼしを抑え、購買保証は、成果が明確な費用投下で無駄打ちを最小化します。販促市場の巨大な重力を、生活者起点へと引き寄せるエンジンが回り始めました。
何が始まったのか――一つの窓口で複数アプリへ一斉展開
クラシルリテールネットワークは、メーカーや小売が個別媒体ごとに交渉や実装を繰り返す負荷を解消し、一つの窓口に販促案件を預けるだけで、提携する複数のアプリに一斉配信できる点が最大の特長です。メッセージの設計、対象商品の定義、期間、還元条件などを一括管理し、各アプリの文脈に応じた表示で生活者に届けます。日々の買い物に密着した設計が徹底され、スーパーやドラッグストアで購入したレシートの提出でポイントが還元されるため、生活者の行動負担は最小限です。メディア側は営業や運用の追加コストをほとんどかけることなく収益源を拡張できます。
仕組みの中核――レシート認識と横断オペレーションがつなぐ実売
仕組みの中核にはレシートの文字情報を機械的に読み取る認識技術と、アプリ間をまたぐ配信オペレーションがあります。レシート画像から対象商品名、数量、購入日時、店舗、金額などを抽出し、販促条件への合致を自動判定します。これにより、同一キャンペーンを複数アプリに載せても検証作業が肥大化せず、生活者の購買を迅速に還元へつなげられます。さらに、来店や閲覧の行動ログ、コンテンツ嗜好の信号などと組み合わせたセグメンテーションにより、企画意図に沿った人へ確度の高いタイミングで情報を届ける基盤も整います。媒体面の露出と店頭での実売が一本のデータ連鎖になったとき、販促活動は初めて「効いた理由」を説明できる段階に到達します。
実績が示す手応え――調理文脈がバスケットを押し上げる
実績の芽もすでに見えています。食体験型の共同企画では、対象商品の購入と調理写真の投稿を促す還元設計によって、総合スーパーやスーパーマーケットでの買い上げ点数と金額が明確に引き上がりました。ある取り組みでは、バスケット単価が一割以上伸長し、周辺食材や調味料の同時購入が促進されています。とりわけ、特定の共同施策では総合スーパーにおけるバスケット単価のリフトが一一三・九%、スーパーマーケットでも一一二・九%に達しています。単品訴求ではなく、調理という文脈に沿って商品を提案することで、食卓全体の構成が自然に組み上がり、結果として関連購買が増える。デジタルでクロスマーチャンダイジングを再現し、しかも投稿インセンティブが“使い切り”を後押しするため、購入した食材が実際の食卓に乗る確率が高まるのです。さらにこの取り組みでは、対象商品を三十一点に広げ、十種類のレシピ実践で追加還元を設けるなど、作って食べる体験を軸に還元を設計しています。販促が単発の値引きではなく、生活行動のデザインとして機能し始めています。
広告主・小売・メディアの三方良し――それぞれの勝ち筋
広告主にとっての価値は三つに集約されます。第一に、運用の集約による機動力です。販促の現場は本来、スピードが勝負です。にもかかわらず媒体ごとの個別折衝、素材準備、承認、レポートのバラバラな形式が意思決定を遅らせてきました。横断配信の採用は、企画から実装、検証、報告までのタイムラインを圧縮し、季節商材や新商品の立ち上げに必要な「リードタイムの短縮」を実現します。第二に、成果の透明性です。購買保証というルールは、投下費用が実売と連動するため、説明責任に耐えうる投資になります。第三に、売場連携の強化です。店頭の施策とメディア施策が同時に回ることで、小売バイヤーとの商談に「確実に売れる販促」という新しい武器を持ち込めます。
小売にとっての価値は、来店と買い上げの質を高める点にあります。店舗オペレーションは限られた人員と売場で回っています。すべての棚でクロス陳列や企画を組むことは困難です。そこで、デジタル上でメニュー起点の需要を作り、来店直前から店頭にかけて購買導線を設計する。結果として、同じ来店でも買い上げ点数が増え、粗利と在庫の回転が安定します。さらに、生活者の購買データが店舗横断で集約されることで、属人的だった企画の良し悪しが可視化され、再現可能なナレッジへと昇華されます。
パートナーアプリにとっては、既存の利用体験を崩さずに収益ポテンシャルを拡げるチャンスです。生活者の文脈はアプリごとに異なりますが、還元という価値は横断で通用します。ニュースやライフスタイルの読み物、家計の見える化、移動や健康の記録といった日常的な接点に、無理のない形で“買う理由”を埋め込める。営業や運用の追加コストを抑えられる設計は、メディア運営における人的なボトルネックを解消し、プロダクト開発にリソースを集中する余地を生みます。
生活者体験の変化――お得の「質」が上がる
そして、生活者の体験が変わります。還元が前提のクーポンや値引きと異なり、レシピや体験と結びついた還元は「作って食べる」という具体的な行動を誘発します。結果として、買った食材がきちんと調理され、食費の最適化と満足度の両立につながる。さらに、複数アプリでキャンペーンを見つけやすくなることで、機会損失が減り、生活者は賢く・楽しく・無理なくお得を積み上げられます。データの提供に関しても、適切な合意と管理のもとで、自分の購買データがより良い提案に戻ってくるという実感が育ちます。
競合と差異化――閉じた生態系か、開かれた横断網か
競合との比較も重要です。巨大な会員基盤を持つプラットフォームには、レシートを購買証明とする成果報酬型の仕組みがすでに存在します。そこでは一社のエコシステムの内側で広告から還元までが完結します。一方、クラシルリテールネットワークは、特定企業の囲い込みではなく、複数の独立したアプリを結ぶ開かれた横断網であることが差異化の核です。さらに、購買喚起のコンテンツとしてレシピや暮らしの知が中核にあるため、単なるポイント獲得行動に終わらず、文脈に沿った自然な購買が生まれやすい。実店舗の購買データを広範に束ねる老舗のネットワークはデータ量で強みを持ちますが、生活者の目線に立った接点設計という観点で、クラシルの強みは補完的であり、共進化も見込めます。
市場環境の追い風――データと人手不足と物価の三層圧力
市場環境は追い風です。広告の世界ではファーストパーティデータの価値が高まり、サードパーティクッキーの後退により、たしかな購買の記録に裏打ちされた施策が求められています。販促の世界では、紙の折込が縮小し、店頭の人手不足と売場の限界から、デジタルに企画の場を移す必要が生じています。生活者の側では、物価高のなかで「お得の質」が問われ、単なる値引きではなく、余らせず使い切れる提案が評価されています。これら三つのベクトルが交点で重なる地点に、横断かつ購買保証のネットワークが位置しています。
導入の実務――九十日で一周する検証サイクル
導入の進め方を具体化しましょう。最初の三十日間で、対象カテゴリと季節要因、在庫状況、競合の販促カレンダーを棚卸しします。次の三十日間で、レシピや使い方の物語を核に、主力商品と関連商品の束ね方を設計し、対象アプリのタッチポイントに沿ってクリエイティブを用意します。最後の三十日間で、横断配信を走らせ、リアルタイムの指標を見ながら還元条件や訴求面の配置を微調整します。九十日で一つの検証サイクルを回し、得られた知見を店頭企画や取引先との商談資料に落とし込みます。以降は、学習済みのセグメントとクリエイティブのライブラリに基づき、季節ごとの定例施策として稼働させます。
計測と学習――短期と中期を分けて、行動の連鎖を捉える
計測の設計では、短期と中期を分けて捉える視点が重要です。短期では、対象商品の購入数、バスケット単価、同時購入の組み合わせ、来店頻度、レシピ閲覧から購入までの転換率を追います。中期では、カテゴリのスイッチ率、ブランドの再購買率、世帯内の使用者増減、平均単価の変化を評価します。加えて、地域別や業態別の反応差を可視化し、チェーンごとの商談や出荷計画に反映させると、ネットワークの価値は一段深まります。
クリエイティブ設計――時間軸に寄り添う提案で「背中を押す」
クリエイティブの原則も押さえておきたいポイントです。料理や暮らしの提案は、生活者が今夜・今週・今月のどの時間軸で意思決定しているかに合わせます。今夜の献立なら、十五分で完成する主菜と二品の副菜、合計の目安予算と冷蔵庫のあり物の活用ヒントを提示する。今週のまとめ買いなら、作り置きの段取りと保存のコツ、週末のごほうびメニューまでの流れを設計する。今月の健康目標なら、塩分やたんぱく質、食物繊維といった栄養の視点で、無理なく達成できるスケジュールを示す。還元は、その背中をそっと押す小さなご褒美として添えます。
組織の横断――四者連携でボトルネックを解体する
組織面では、販促と営業、サプライチェーン、法務、情報システムの四者連携が成功のカギになります。販促が設計した需要の波を営業が売場に落とし込み、サプライチェーンが在庫と物流を最適化し、法務が表示や規約の適正を担保し、情報システムがデータの流通を滑らかにする。横断網は、企業内部の横断も促す触媒です。部門横断の定例会を設け、共通のダッシュボードで同じ数字を見る文化を育てるべきです。
信頼とガバナンス――透明でわかりやすい体験設計
生活者の信頼を獲得するためには、透明性の高いコミュニケーションが不可欠です。どのデータを何の目的で使い、どのような便益が戻るのかを、難解な語を避けて伝えます。オプトインの導線は簡潔に、同意の取り消しやデータの削除請求の手段も明確に用意します。還元の条件や上限、対象外の注意事項は、小さな文字ではなく、理解可能な言葉でわかりやすく配置する。信頼は、最初の数回の体験で決定的に形づくられます。
これからの販促――OS化する横断網が標準になる
この横断網が普及した先に見える姿は、販促のOS化です。媒体計画、クリエイティブ制作、配信、来店促進、購買、還元、検証、学習という一連のサイクルが、同じ設計思想で回る。企業間、アプリ間、売場間の隔たりが薄まり、生活者の一日の流れに広告と販促が溶け込んでいく。販促は、値引きの手段から、需要の設計学へ。企業の競争は、単価や露出量の競い合いから、行動の理解と設計の巧拙へと重心を移します。
課題の直視――還元の健全性、在庫の追随、店舗の受け皿
現場に残る課題も、正面から捉えましょう。例えば、過度な還元は短期の売上を押し上げる一方で、中長期の価格の健全性を損なう恐れがあります。したがって、還元は「値下げの代替」ではなく「選択の後押し」として設計し、上限と頻度を管理する。もう一つは、在庫の追随性です。横断配信の火力は高く、売り切れや欠品が発生しやすい。需要の波形を学習し、供給側とあらかじめ調整する運用習熟が求められます。さらに、店舗ごとの受け皿にも差があります。実店舗の体験を損なわないよう、店頭導線や従業員のオペレーション負荷にも配慮した設計が必要です。
結論――点から線へ、線から面へ。販促の基盤が入れ替わる
最後に、生活者の時間を尊重するという原則を掲げます。還元が目的化すると、短い快感の反復が長い倦怠を生みます。レシピや暮らしの知恵は、時間を豊かにするための道具です。横断網の成功は、生活者の一日の質が上がったと感じられるかどうかにかかっています。料理が少し楽になり、家計が少し軽くなり、食卓の会話が少し増える。その積み重ねが企業の成果に結びつく未来を、設計し続けることが大切です。
販促の地図は、これから描き替えられます。媒体ごとの最適化では到達できなかった面の最適化が、横断と購買保証の交点で可能になります。誰よりも早く、誰よりも丁寧に、生活者の行動文脈を読み解き、最小の摩擦で最大の満足を届ける企業が、次の勝者になります。横断網が提示した新しい当たり前を、今日から自社の実務に接続してください。
当社では、AI超特化型・自立進化広告運用マシン「NovaSphere」を提供しています。もしこの記事を読んで
・理屈はわかったけど自社でやるとなると不安
・自社のアカウントや商品でオーダーメイドでやっておいてほしい
・記事に書いてない問題点が発生している
・記事を読んでもよくわからなかった
など思った方は、ぜひ下記のページをご覧ください。手っ取り早く解消しましょう
▼AI超特化型・自立進化広告運用マシンNovaSphere▼

![デジマラボ [Digima Labo] by NpvaSphere(旧チャンキョメ)](https://digima-labo.com/wp-content/uploads/2023/06/logo_dezimalabo_2212763.png)